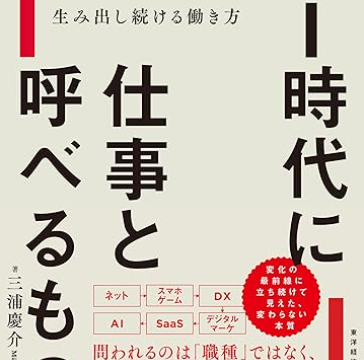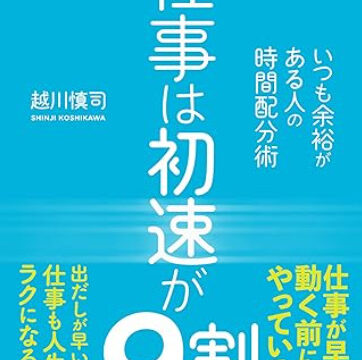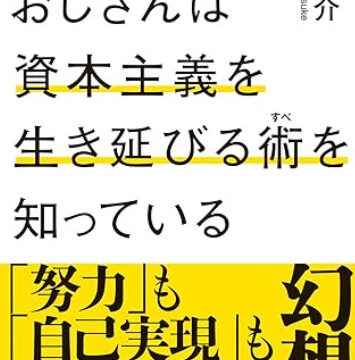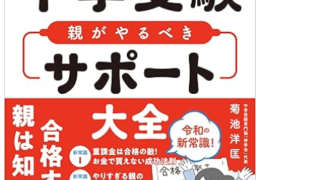【終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実】感想・レビュー
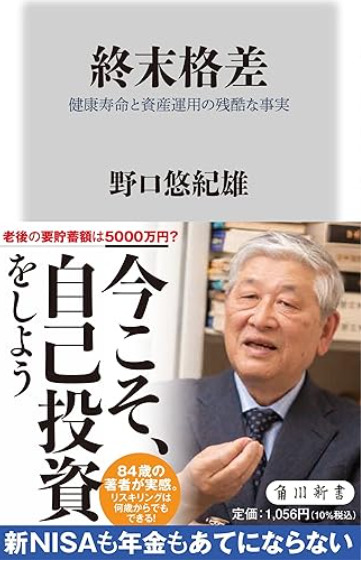
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
親世代の老後生活を見ると、
残酷な現実を目の当たりにします。
悠々自適に生活している人もいれば、
老体に鞭打って働く人もいる。
この差はどこから生まれたのでしょうか?

個人的に思うのは、
厚生年金の加入有無ですね。
会社員は厚生年金を貰い、
悠々自適に過ごしている人が多い。
でも自営業は国民年金のみなので、
老後も働き続けている人が多い。
国民年金は満額でも約6.9万/月。
これでは足りないですよね。

さて、
会社員なら老後も安泰でしょうか?
そうとも言い切れないです。

昔は終身雇用だったので、
定年まで働きその収入で過ごす。
老後は厚生年金を貰い、
悠々自適に過ごす。
これが当たり前でしたが、
今は終身雇用が保証されない時代です。
リストラや役職定年、
非正規雇用への転換で給与減もある。
年金を貰う前に生活資金が底をつき、
年金受給までもたないケースもありえる。
年金以前の問題ですよね。

では、
どうすればいいでしょうか?
現役時代から資産形成に励み、
何が起きても耐えられる準備をする。
でも、
どう準備すればいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
年金制度はどうなるか?
資産形成をどのように行えば良いか?
いくら貯めればよいのか?
本書を読むとよくわかります。
老後を迎えるにあたり、
もう1つ大切なことがあります。
それは健康への知識です。

健康を疎かにしていると、
老後に莫大な金額がかかります。
もし大病を患ってしまうと、
家族にも迷惑をかけることになります。
最終的に病気は避けられないけど、
頻繁に繰り返すことは避けたい。
健康寿命を維持するのも、
快適に老後を過ごすためには大切です。
本書はその点にも触れていますので、
ぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログでご紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:老後資金としていくら必要か?
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第1章のまとめ
<ポイント>
・「2000万貯めれば十分なのか?」この答えは未だにはっきりしない
・将来の年金水準が低下したり、支給開始年齢が引き上げられたりすれば、用意すべき老後資金は3000万円を超えるだろう
・年金生活者の実態は以下参照
<年金生活者の実態(平均)>
・年金収入:20万円/月
・世帯収入:25.5万円/月
・世帯支出:28.6万円/月
老後2000万問題、
以前大騒ぎになりましたよね。
その当時よりインフレが進み、
2000万円では足りない説も出てます。
ただし、
実際のところはハッキリしないらしい。

年金生活者の実態を世帯別に見ると、
支出が収入を約3万円オーバーしてます。
年単位だと約36万円なので、
不足額は何となくイメージはつきます。
65歳から年金をもらうとすれば、
75歳までの10年間なら約360万円不足。
仮に30年と計算した場合、
約1080万円の不足となります。
2000万円用意して余るようなら、
それはそれでよいのでは?
悠々自適に生活できるわけだし、
2000万を目安にするのはアリですね。
第2章:投資戦略で老後を守れるのか?
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第2章のまとめ
<ポイント>
・新NISAが爆発的な人気を集めたが、これが老後資金問題の救いの神になるとは限らない
・確実に儲けられる方法はない。マーケットを出し抜くことはできない
・インフレ時代には、預金ではなく株式投資すべきだという意見があるが、インフレになれば預金金利が上昇することに注意が必要だ
新NISAで老後資金を用意できるか?
投資次第ですね。
投資で確実に儲かる方法はないので、
投資で損する可能性はある。
老後資金のために投資したのに、
減ってしまったら意味がないですよね。

ただし、
マーケット連動の投信なら、
老後資金を用意できるのでは?
マーケットを出し抜けないなら、
マーケットの波に乗ればいい。
株式市場を長期的に見ると、
緩やかに上昇するのが過去の歴史。
たとえば米国市場に連動する投信を買い、
長期保有すれば利益が出る確率は高い。

新NISAの生涯投資枠は1800万です。
もし米国市場連動型の投信、
たとえばS&P500に1800万投資したら?
長期運用なら2000万円も夢ではない。
むしろ確率は高いと個人的には思う。
預金金利の上昇を期待して、
銀行預金で準備する方が時間はかかる。
コチラの本がわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。

第3章:団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第3章のまとめ
<ポイント>
・厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられ、人々は退職を遅らせることで対処したが、企業は非正規化を進めた。高年齢雇用安定法で、非正規化が難しくなり、しわ寄せが50代に及んでいる
・年金受給まで正規雇用者を続けるのが難しい男性雇用者は、50歳代の中頃までは正規が多いが、その後非正規雇用の比率が高まる
・非正規の場合、物価が上昇しても賃金上昇を期待するのは難しいだろう
50代の中頃までに、
いかに資産形成できるか?
理想は65歳の年金受給開始まで、
資産形成に励むことです。
65歳以降は年金をベースに生活し、
不足が出たら貯金を切り崩す。
これができれば、
老後は悠々自適な生活を送れる。

でも50代半ばで非正規になり、
生活が厳しくなる場合はどうするか?
年金受給開始まで凌ぐために、
資産切り崩しの可能性もある。
切り崩せる資産は多ければ多いほど良い。
つまり、
切り崩しが始まる前までに、
いくら資産を築けたかが勝負となる。

老後2000万を目安にした場合、
50代半ばなら1500万の資産は欲しい。
55歳で1500万の資産があれば、
残り10年で500万の資産形成はできる。
1年で50万ずつの貯金で達成できるし。
ただし不測の事態を考えれば、
50代半ばで2000万が理想かも。
若い頃から資産形成に励まないと、
不測の事態に耐えられないですね。
第4章:公的年金は老後生活の支柱となるか?
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第4章のまとめ
<ポイント>
・財政検証によれば、実質賃金に関する現実的な見通しの下では、公的年金の所得代替率は、現在に比べて大きく落ち込む。老後のための要貯蓄額は、3000万程度になる。場合によっては5000万円を超える
・日本の公的年金制度が抱える問題として、「第3号被保険者問題」がある
・今後も人口高齢化が続くので、年金制度を維持する困難さは増す。これに対処するため、年金支給開始年齢の引き上げが議論の対象となる可能性がある
3000万や5000万の話は、
非現実的かなと思いますね。
50代の貯蓄の中央値、
1000万未満なのが日本の実態です。
平均値は1000万を超えるけど、
大金持ちが平均値を上げてるので、
あまり参考になりません。
3000万や5000万が必要な場合、
はたして何割が到達できるのか?
むしろ大半が到達できず、
国の財政はさらに悪化しますよね。

一番の問題は第3号でしょうね。
共働き家庭が増えて、
昔よりは第3号も減っています。
それでもまだ、
800万人以上います。
もし第3号も保険料納付になったら、
破綻する家庭も出るでしょうね。

年金引き上げは可能性が高そうです。
今は65歳から年金支給開始ですが、
いずれは70歳になる可能性は高い。
70歳まで働けるかは、
だれにもわからないですよね。
働けるうちに資産を築くか、
70歳までどうにか働くの2択かも。

早めに資産を築き、
個人ビジネスで稼ぎ続けるのが最強かな、
と個人的には思います。
資産形成は新NISA、
個人ビジネスは副業から始めるのが良い。
副業はコチラの本がわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。
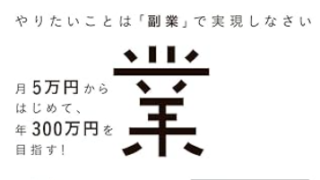
第5章:介護保険は破綻しないか?
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第5章のまとめ
<ポイント>
・要支援・要介護者のほとんどは、自宅に住み続けて介護保険のサービスを受けている
・有料老人ホームなどの施設に入るのは、病気で入院して退院後に要介護になった人や、認知症の人が多い
・介護分野の就労者が激減している
要介護3と認定されないと、
特別養護老人ホームは入居できないです。
要介護3はなかなか認定されず、
私の親が苦労しているのを見ました。
私の祖父母が要介護2の時、
もはや1人で生活は無理でした。
でも特養に入居できず、
デイサービスしか利用できず。
デイサービスに通わない日は、
だれかの介護は避けられない状態に。

高齢化&少子化を考えると、
入居はますます難しいでしょうね。
入居希望者は増えるけど、
介護する人は減る。
いかに健康寿命を延ばすかが、
老後のポイントですね。
介護士の友人に聞いたのですが、
↓の2つが衰えると要介護になりやすい。
・食べる量が減る
・動く量が減る
健康寿命を延ばすために、
老後はウォーキングする予定です。
今は運動してるからいいけど、
いずれは厳しいだろうと思ってます。
運動でケガして寝たきりになると、
高齢者は一気に衰えるので。
コチラの本がわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。
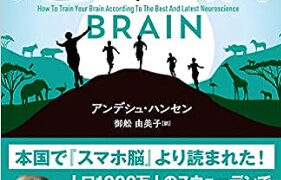
第6章:期待される医療技術の進歩
第6章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第6章のまとめ
<ポイント>
・ips細胞等の幹細胞を用いる「再生・細胞医療」、「遺伝子治療」、「免疫系を基盤とする治療」、がんや認知症の早期診断などでの進歩が期待される
・オンライン診断は重要だが、日本ではなかなか進まない
・2040年の医療需給を見ると、医療関係者は介護保険者ほどは増加しない。急性期医療から慢性期医療への転換が進む
日本人の死因1位は「がん」です。
がんは場所によって生存率が異なり、
極端に低いのは膵臓です。
膵臓がんは早期発見が難しく、
見つかった時にはもう遅いのです。
がんの特効薬は難しくても、
早期発見技術が上がってほしいですね。

認知症も悩ましい病気です。
認知症は早期発見できたとしても、
がんのように完全に治ることはない。
高齢になれば認知症リスクも高まり、
周りの家族にも介護で悪影響が出る。
認知症の特効薬もないけど、
症状を遅らせる薬が出てほしいですね。
第7章:高齢者の負担増が進む
第7章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第7章のまとめ
<ポイント>
・医療保険や介護保険で、保険料や自己負担率の引き上げが行われ、高齢者の負担が増加している
・高齢者も社会保険の負担を受け持つべきだとする「全世代型社会保障」の考えに沿った制度改定だ
・伝統的な社会では介護は家族内の相互扶助だったが、いま介護は社会化された
将来は家族に介護してもらう、
という時代ではないですね。
共働き家庭も増えてますし、
介護する家族が家にいない。
介護保険の利用も必要だけど、
高齢者の自己負担も必要になるでしょう。
老後に備える意味でも、
現役時代から資産形成すべきですね。
第8章:終末格差を克服するのは、自分への投資
第8章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第8章のまとめ
<ポイント>
・高齢者が働き続け、社会とのつながりを維持すべきだ。最近目覚ましく発展したリモートワークは、こうした生き方を可能とする強力な手段だ
・過去半世紀間に情報処理技術が著しく進歩した。これは産業構造や企業の姿を大きく変えた。この変化は、高齢者の就業に有利に働いている
・高齢者の就労を妨げる税や社会保障の仕組みを見直すことが必要だ。また、生成AIなどを用いて、個人個人がリスキリングを行なう必要がある
高齢者が働く意味、
2つあると思ってます。
1つは収入。
もう1つは社会とのつながり。
社会とのつながりがあれば、
孤独死を防げる可能性もある。

そうは言うものの、
高齢者が働くのは大変です。
体力低下は避けられず、
若い時と同じようには働けない。
肉体労働は難しいけど、
頭脳労働は意外と可能性がある。
いまはAI全盛の時代なので、
頭脳の衰えをAIでカバーできる。

そう考えると、
高齢者にもAIスキルは必要です。
リスキリングで何を学ぶべきか?
個人的にはAIだと思ってます。
AIについては、
コチラの本がわかりやすいです。
ChatGPTはAIの登竜門。
無料で操作できるのでオススメです。
ご興味あればぜひご覧ください。
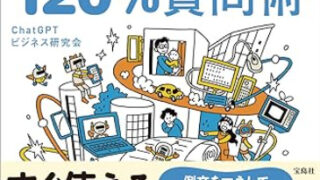
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:老後資金としていくら必要か?
・第1章のまとめ
<ポイント>
・「2000万貯めれば十分なのか?」この答えは未だにはっきりしない
・将来の年金水準が低下したり、支給開始年齢が引き上げられたりすれば、用意すべき老後資金は3000万円を超えるだろう
・年金生活者の実態は以下参照
<年金生活者の実態(平均)>
・年金収入:20万円/月
・世帯収入:25.5万円/月
・世帯支出:28.6万円/月
第2章:投資戦略で老後を守れるのか?
・第2章のまとめ
<ポイント>
・新NISAが爆発的な人気を集めたが、これが老後資金問題の救いの神になるとは限らない
・確実に儲けられる方法はない。マーケットを出し抜くことはできない
・インフレ時代には、預金ではなく株式投資すべきだという意見があるが、インフレになれば預金金利が上昇することに注意が必要だ

第3章:団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後
・第3章のまとめ
<ポイント>
・厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられ、人々は退職を遅らせることで対処したが、企業は非正規化を進めた。高年齢雇用安定法で、非正規化が難しくなり、しわ寄せが50代に及んでいる
・年金受給まで正規雇用者を続けるのが難しい男性雇用者は、50歳代の中頃までは正規が多いが、その後非正規雇用の比率が高まる
・非正規の場合、物価が上昇しても賃金上昇を期待するのは難しいだろう
第4章:公的年金は老後生活の支柱となるか?
・第4章のまとめ
<ポイント>
・財政検証によれば、実質賃金に関する現実的な見通しの下では、公的年金の所得代替率は、現在に比べて大きく落ち込む。老後のための要貯蓄額は、3000万程度になる。場合によっては5000万円を超える
・日本の公的年金制度が抱える問題として、「第3号被保険者問題」がある
・今後も人口高齢化が続くので、年金制度を維持する困難さは増す。これに対処するため、年金支給開始年齢の引き上げが議論の対象となる可能性がある
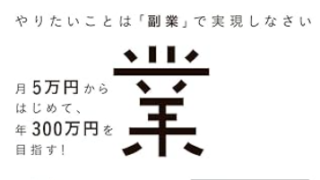
第5章:介護保険は破綻しないか?
・第5章のまとめ
<ポイント>
・要支援・要介護者のほとんどは、自宅に住み続けて介護保険のサービスを受けている
・有料老人ホームなどの施設に入るのは、病気で入院して退院後に要介護になった人や、認知症の人が多い
・介護分野の就労者が激減している
第6章:期待される医療技術の進歩
・第6章のまとめ
<ポイント>
・ips細胞等の幹細胞を用いる「再生・細胞医療」、「遺伝子治療」、「免疫系を基盤とする治療」、がんや認知症の早期診断などでの進歩が期待される
・オンライン診断は重要だが、日本ではなかなか進まない
・2040年の医療需給を見ると、医療関係者は介護保険者ほどは増加しない。急性期医療から慢性期医療への転換が進む
第7章:高齢者の負担増が進む
・第7章のまとめ
<ポイント>
・医療保険や介護保険で、保険料や自己負担率の引き上げが行われ、高齢者の負担が増加している
・高齢者も社会保険の負担を受け持つべきだとする「全世代型社会保障」の考えに沿った制度改定だ
・伝統的な社会では介護は家族内の相互扶助だったが、いま介護は社会化された
第8章:終末格差を克服するのは、自分への投資
・第8章のまとめ
<ポイント>
・高齢者が働き続け、社会とのつながりを維持すべきだ。最近目覚ましく発展したリモートワークは、こうした生き方を可能とする強力な手段だ
・過去半世紀間に情報処理技術が著しく進歩した。これは産業構造や企業の姿を大きく変えた。この変化は、高齢者の就業に有利に働いている
・高齢者の就労を妨げる税や社会保障の仕組みを見直すことが必要だ。また、生成AIなどを用いて、個人個人がリスキリングを行なう必要がある
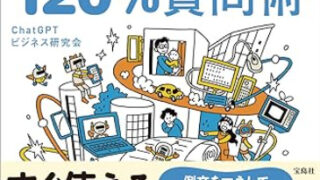
まとめ
老後資金がいくら必要なのか?
ハッキリとした金額はわからない。
でも年金だけでは不足する、
というのは何となく想像できる。
いまから資産形成を行い、
老後資金の確保が必要なのは間違いない。
老後資金の確保は、
貯蓄でも投資でもどちらでもOKですね。

老後資金がいくら必要か不明なので、
できる限り多い方が安心です。
できる限り多い方が良い理由、
実はもう1つあります。
それは50代以降に給与減となり、
貯蓄を切り崩すケースもありえるから。
役職定年やリストラだったり、
非正規雇用への転換も考えられます。
老後のために用意する資金だけど、
やむを得ず使うのも想定した方がいい。

資産形成が難しい方は、
高齢になっても働く道を考えた方がいい。
身体機能は徐々に衰えるので、
できれば頭脳労働がベストです。
頭脳も衰えるけど、
AIで補うことができる。
高齢者が稼ぐ観点で考えると、
肉体労働より頭脳労働の方が現実的です。

ざっと本書を読んだ感想ですが、
とても現実に即した本だと思います。
悲観的な内容も多いけど、
その分だけ対策も考えやすい。
悲観的に考えて対策を練れば、
仮に楽観的な状況なれば余裕が出る。
その逆は本当に悲惨な状況になる。
それでは困りますよね。
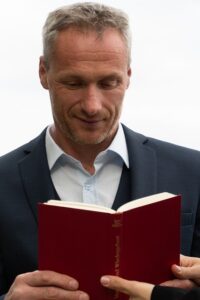
悠々自適な老後を過ごしたい方。
いますぐ本書をお買い求めください。
歳を取ると、
1年過ぎるのが早く感じますよね。
皆さんの想像以上に、
老後は早めに訪れます。
将来準備すればいいと考えていると、
あっという間に老後を迎えて破産します。
幸せな老後を迎えるために、
今から準備をしましょう。
本書のお値段は1,056円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学4年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)