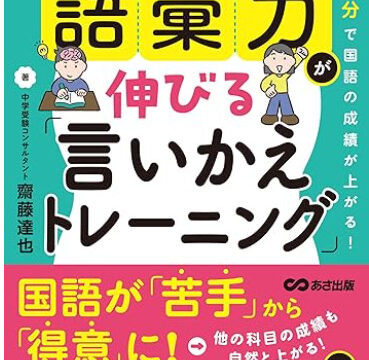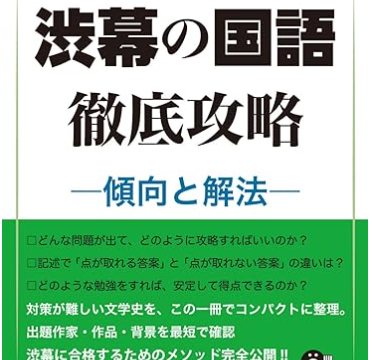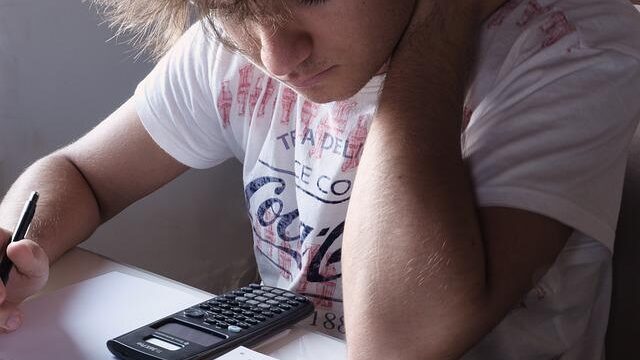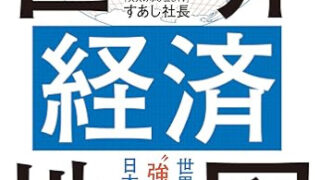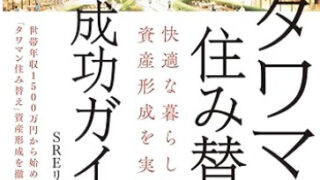【なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール】感想・レビュー
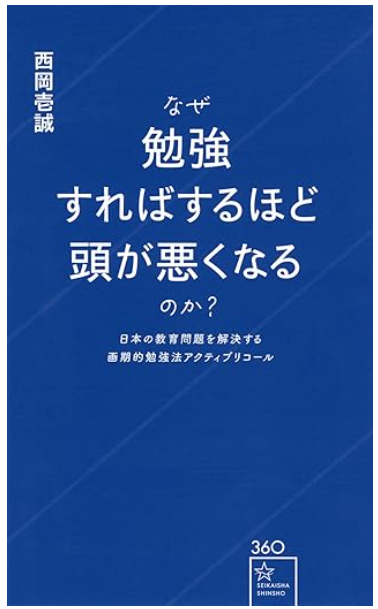
(2026/2/2更新)
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』
なぜこんなに勉強しているのに
成績が伴わないのだろうか?
子どもの勉強を見ていて、
そう感じたことありませんか?
テスト前にテキストを読み、
問題演習もバッチリこなしたのに。
それはもしかすると、
テキストの問題かもしれません。
テキストに問題あり?
そんなことあるの?
と思うかもしれませんが、
実は大アリです。

最近の参考書はどれも見やすく、
要点が整理されて効率よく学べます。
しかし、
整理されすぎているが故に、
子どもの思考力が深まらないのです。
最短で正解に辿り着けるなら、
わざわざ考える必要ないですよね。
テストには、
思考力を問う問題も出題されます。
このような問題に正解できないと、
いくら勉強しても成績に結びつかない、
これでは困りますよね。

では、
どうすればいいでしょうか?
思考力を深める勉強をすればいい。
でも、
どうやってやればいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』
思考力深める勉強法と書かれているのは、
アクティブリコールです。
「覚える」ではなく、
「思い出す」ことを重視する勉強法。
思い出す際に紙へ書き出すのですが、
これが思考力を深める訓練になる。

たとえば日本史の例だと、
794年に平安京に遷都します。
単発で覚えることが多いけど、
ではなぜ遷都したのか?
実は、
コチラの流れ(↓)があるのです。
これが思考力の勉強ですよね。
テストで出題されても答えられる。
・荘園によって公地公民制が崩壊
<ポイント>
・租・庸・調などの負担に耐えかねて逃げ出す者や、戸籍をごまかして税を逃れる者がいた
・三世一身の法や墾田永年私財法が制定されたが、経済力のある貴族や寺社が逃げてきた農民などを使って開墾し、自分の土地を広げていった(のちの荘園となる)
・荘園を多く手に入れることで貴族が力をつけ、寺社(仏教勢力)が政治に口出しするようになり、桓武天皇は奈良を離れようとする(のちの平安京遷都につながる)
私の子ども、
歴史の成績が伸び悩んでます。
何か良い勉強法はないだろうか?
ということで本書を購入しました。
歴史の勉強の実践例が書かれているので、
とても参考になります。
もちろん他の科目も本書にあるので、
ぜひ参考にしてみてください。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:日本が直面する教育の課題とは?
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・読みやすい、要点のまとまった参考書の問題点
<ポイント>
・「親切すぎる設計」は、逆に子どもの学力を下げてしまう危険性を孕んでいる
・最短で正解に辿り着く方法が整備されすぎているせいで、「悩む」「迷う」「間違える」といった、思考を深めるために不可欠なプロセスが省略されてしまっている
・親切すぎる参考書は、接触する情報量が多すぎて結局何を覚えればいいのかがわからなくなり、忘れやすくなってしまう
子どもの歴史の勉強を見ていると、
実感しますね。
テキストはまとまってるけど、
せっかく覚えたのに忘れてしまう。
知識の暗記に留まっていて、
時代背景の理解が甘い。
歴史のテストで失敗した例、
コチラをご覧ください(↓)

歴史対策として、
2つの本を読ませています。
当時の時代背景は何か?
その時はだれが支配者か?
どのような問題が起こったのか?
SAPIXのテキストだと、
時代ごとにテキストが分かれてしまう。
コチラの本なら通しで読めるので、
時代の流れを理解できます。
次章のアクティブリコールを実践すれば、
歴史の理解が深まるかもしれませんね。
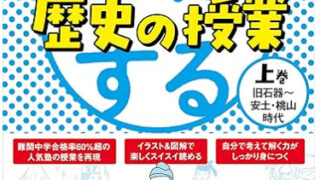
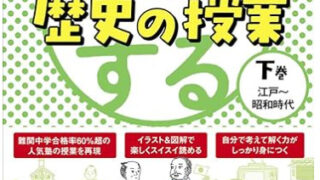
第2章:アクティブリコールとは何か?
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・思い出すことの重要性
<アクティブリコールとは>
・やったことを後から思い出す勉強法
<ポイント>
・「覚える」と「思い出す」は異なる脳の活動である
・「記憶が苦手だ」「暗記が苦手だ」と思っている人でも、意外と「覚える」ことを得意なのです
・苦手なのは「思い出す」ことであって、「思い出す」練習さえうまくできれば、誰でも記憶や暗記に関する悩みを解消できる
言われてみればたしかに!
おもしろい発想ですね。
その場では覚えられても、
数日後に思い出すのは難しい。
アクティブリコールの勉強法、
コチラ(↓)と書かれてますね。
夜寝る前の15分がオススメらしい。
・1日の終わりに白紙の紙を1枚用意する
・勉強したことを思いつく限り書いてみる
・ノートを見返して、自分の知識の穴を見つける
私の子どもで実践するなら、
歴史の勉強ですね。
SAPIXのテキストや歴史の本を読み、
夜寝る前に書き出してみる。
どこまで覚えているか?
理解不十分な箇所はどこか?
歴史の理解が深まり、
成績アップに結びつくと嬉しいですね。
第3章:科目・分野別、シチュエーション別アクティブリコール活用法
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・ストーリー暗記型の科目-世界史・日本史など
<ポイント>
①「なぜこの出来事が起こったのか?」「この出来事の後に何が起きたのか?」といった因果関係を意識して、流れの中で知識を理解しましょう
②年号や細かい人名・用語の正確さをはじめから気にしすぎる必要はない
③「正確に書く」よりも「つなげて理解する」ことを重視し、流れ・因果・構造で記憶を可視化する
②が意外でしたね。
年号/人名/用語はテストに出るので、
正確性が重要かと思ってました。
③正確性よりも流れ重視ですね。
歴史は時代の流れなのでこれは正しい。
子どもにやらせたらどうなるかな?
楽しみですね。
第4章:アクティブリコールをやってみてわかったこと
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・日本史 高校2年生 友渕莉子さん
<ポイント>
①自分ではわかっていたつもりでも、実際に書き出してみると、まだまだ知識を広げきれていなかったことに気づく
②アクティブリコールでは内容をある程度理解していないと書くことができないため、授業中も「理解しよう」と意識して聞くようになる
③書いて終わりではなく、そのあと教科書などで答え合わせをしながら、自分の抜けていたところや間違っていたところを明確にしていくことが大切
②はとても重要ですね。
授業を真剣に聞かない子どもは、
意外と多いので。
私が子どもに解説してる時も、
「ボーっと聞いてるな」
と思うことは何度もありました。
「いま教えたことを説明してみて」
と聞くと曖昧な説明に終わる。

授業をきちんと聞いても、
おそらく完璧には書けないでしょう。
そこで重要なのが、
③振り返りかなと思います。
「書く→振り返る」を繰り返せば、
思い出す力も養われますよね。
これで歴史の成績が上がるといいけど。
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:日本が直面する教育の課題とは?
・読みやすい、要点のまとまった参考書の問題点
<ポイント>
・「親切すぎる設計」は、逆に子どもの学力を下げてしまう危険性を孕んでいる
・最短で正解に辿り着く方法が整備されすぎているせいで、「悩む」「迷う」「間違える」といった、思考を深めるために不可欠なプロセスが省略されてしまっている
・親切すぎる参考書は、接触する情報量が多すぎて結局何を覚えればいいのかがわからなくなり、忘れやすくなってしまう

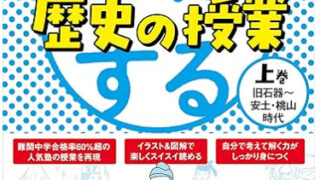
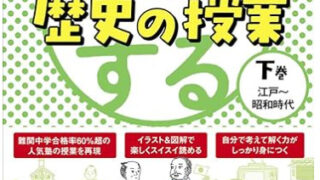
第2章:アクティブリコールとは何か?
・思い出すことの重要性
<アクティブリコールとは>
・やったことを後から思い出す勉強法
<ポイント>
・「覚える」と「思い出す」は異なる脳の活動である
・「記憶が苦手だ」「暗記が苦手だ」と思っている人でも、意外と「覚える」ことを得意なのです
・苦手なのは「思い出す」ことであって、「思い出す」練習さえうまくできれば、誰でも記憶や暗記に関する悩みを解消できる
・1日の終わりに白紙の紙を1枚用意する
・勉強したことを思いつく限り書いてみる
・ノートを見返して、自分の知識の穴を見つける
第3章:科目・分野別、シチュエーション別アクティブリコール活用法
・ストーリー暗記型の科目-世界史・日本史など
<ポイント>
①「なぜこの出来事が起こったのか?」「この出来事の後に何が起きたのか?」といった因果関係を意識して、流れの中で知識を理解しましょう
②年号や細かい人名・用語の正確さをはじめから気にしすぎる必要はない
③「正確に書く」よりも「つなげて理解する」ことを重視し、流れ・因果・構造で記憶を可視化する
第4章:アクティブリコールをやってみてわかったこと
・日本史 高校2年生 友渕莉子さん
<ポイント>
①自分ではわかっていたつもりでも、実際に書き出してみると、まだまだ知識を広げきれていなかったことに気づく
②アクティブリコールでは内容をある程度理解していないと書くことができないため、授業中も「理解しよう」と意識して聞くようになる
③書いて終わりではなく、そのあと教科書などで答え合わせをしながら、自分の抜けていたところや間違っていたところを明確にしていくことが大切
まとめ
現代の教育が抱える課題は、
親切すぎる参考書です。
効率よく正解へ導く構成は便利だけど、
思考力を深める過程を奪ってしまう。
その結果、
暗記中心の勉強となり理解が浅くなる。
自分の子どもの歴史学習を見ていても、
実感しますね。
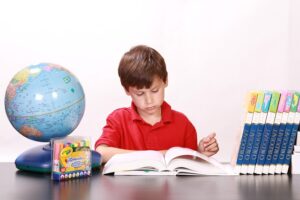
本書で紹介されているのは、
アクティブリコールという学習法です。
「覚える」ではなく、
「思い出す」ことに焦点を当てた内容。
白紙に学んだことを書き出し、
抜け漏れを確認する。
何を覚えているか?
どこが曖昧か?
明確にあぶり出されますね。
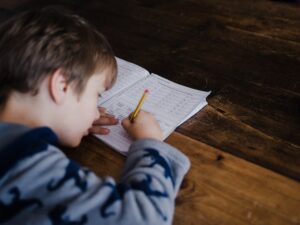
子どもの学習に向けて参考にしたのが、
歴史の学習例です。
年号や用語の正確性よりも、
出来事同士のつながりを重視してます。
なぜその出来事が起きたのか?
次に何が起きたのか?
書き出してみると、
自分の理解度がよくわかる。

高校生の実践例を見ると、
やはり抜けの多さに気づくそうです。
抜けないように授業中の理解度を深め、
書き出し後に教科書と照らし合わせる。
「書く→振り返る」を習慣化することで、
思い出す力が養われると思いますね。

私が本書を購入したのは、
子どもの歴史の成績を上げるためです。
歴史学習の箇所を中心に紹介したけど、
他の科目についても書かれています。
子どもの苦手科目の勉強に、
アクティブリコールを取り入れると、
理解が深まり成績が上がるでしょうね。
子どもの勉強でお悩みの方は、
いますぐ本書を買い求めください。
本書のお値段は1,430円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
・なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)