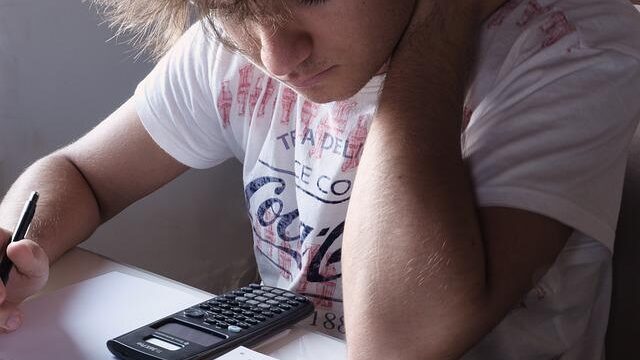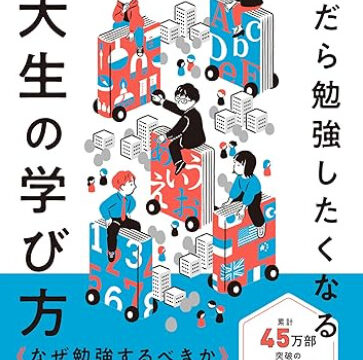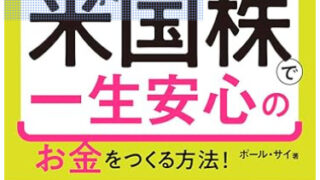【SAPIX 11月度マンスリー確認テスト(小5)】算数大崩れで成績上位5%入りならず。なぜこんなに悪かった?
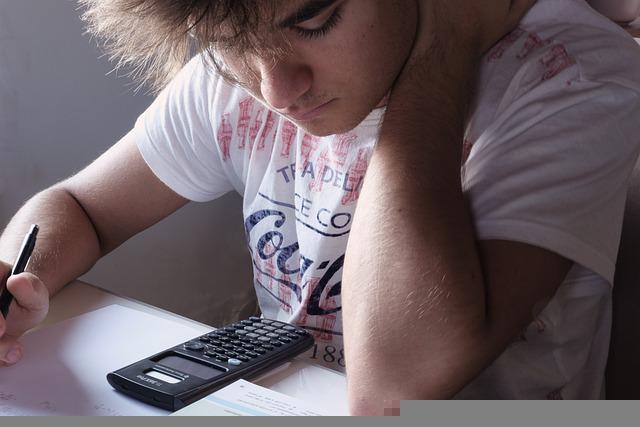
(2025/12/24更新)
はじめまして、はるパパです。
さて、
11/12のテスト結果が返却されました。
前回の結果については、
↓のブログをご覧ください。

成績上位5%以内、
残念ながら達成できませんでした。
テストが終わった日の様子、
採点前答案を見て覚悟はしてたけど。
「算数が全然できなかった」
「社会が難しかった」
採点後答案を見ると、
まさにその言葉通りの結果でした。
特に算数はかなり点を落とし、
テスト自体も苦戦したそうです。

たしかに前半の問題でも、
難しい問題がいくつか混ざってました。
それにして落としすぎ。
凡ミスがなければ、
さすがにもう少し取れましたね。
焦りなのか?
メンタルなのか?
なかなか上手くはいかないものです。

というわけで、
今回のテストを振り返ります。
皆様の参考になれば幸いです。
国語
国語のテスト、
以下の4分野から出題でした。
4科目で最も成績が良かった国語。
1年前は記述で大苦戦してたのに、
徐々に模範解答へ近づいてきた。
どうして伸びたのか?
今回は記述問題に触れてみます。
1.漢字の読み書き
2.ことばの知識・品詞・慣用句
3.説明文の読解
4.物語文の読解
記述解答の練習は、
Bテキストで実施しています。
ノートの上段に、
子どもが記述回答を書きます。
ノートの下段に、
私が模範解答の写しを書きます。
上下を比較して、
回答の不足部分を分析します。
満点にならないポイントを見ると、
3つの誤りに該当することが多い。
①構造の誤り(ex AとBを対立で書かなきゃいけないのに、書いていない)
②要素の誤り(ex A,B,Cの3要素を書かなきゃいけないのに、不足している)
③論点の誤り(ex Aについて書かなきゃいけないのに、Bについて書いている)
一番マズいのは③、
0点になってしまいます。
出題者の意図が読み取れてないので、
ここはじっくり教える必要がある。
①②は部分点が多いですね。
①配点の半分だけ得点とか、
②3要素中2つのみなら配点の2/3点とか。

これを1年かけて教えたら、
急激に点数が伸びましたね。
記述問題は配点12~15点なので、
ここでの点数は大きな差となります。
国語の点数を伸ばすなら、
記述問題の攻略が必須ですね。
算数
算数のテスト、
以下の7分野から出題でした。
今回一番成績が悪かった算数。
これが4科目成績に大きく響いた。
6.7がまったく解けず、
それ以前も凡ミスで落とす有様。
応用問題以外は確実に取ってほしい。
課題だらけなので解説します。
1.計算問題・小問集合
2,比と図形
3,流水算
4,旅人算・時計算
5,比と図形
6,平面図形
7.流水算
1~5の間違いを見ると、
凡ミスがもったいない。
分母と分子を書き間違えたり、
途中式は合ってるのに計算ミスしたり。
普段の学習でも見られるし、
なかなか直らない。
コチラの本に書かれている、
算数のケアレスミスを思い出そう。

6,7も見たけど、
6はそんなに難しくない。
平面図形と言いながら、
単なる比の問題。
これは教えれば解けるかな。
7は問題文自体がかなり複雑で、
残り時間を考えると難しいかも。
正解率がとても悪いし、
これはできなくても仕方ないかも。
理科
理科のテスト、
以下の5分野から出題でした。
前回と変わらず好成績。
理科の苦手意識はもはや過去の話。
でも課題も見つかりましたので、
後ほど解説します。
1.小問集合
2.動物の分類
3.気体の発生
4.溶解度
5.電熱線
課題は3.気体の発生。
ワンポイントアドバイスにあるけど、
↓がおそらく理解できていない。
この周辺の問題を、
集中的に間違えてるので。
テキストの見直しですね。
・酸素が発生する場合は、気体の発生量が過酸化水素水の量で決まる
・水素や二酸化炭素の発生では、2種類の物質の過不足を考え気体の発生量を求める
社会
社会のテスト、
以下の2分野から出題でした。
今回かなり勉強したけど、
思ったほどは伸びなかった社会。
なぜ伸び悩んでいるのか?
なんとなく見えてきました。
今回は伸び悩みの原因について、
詳しく分析します。
1.戦乱に関する問題
2.歴史上の人物に関する問題
歴史の大まかな流れに関しては、
かなり理解しています。
それでも得点が伸び悩むのは、
暗記の偏りが原因かも。
テキストを読んで、
時代の流れ/年号/出来事等を覚える。
でも、
地図帳や資料集の読み込みが足りず、
↓の問題で間違える。
地図帳や資料集をもっと目を通さないと、
今後のテストも取りこぼすかな。
・地理(ex 北朝/南朝の位置)
・建造物の特徴(ex 金閣寺の全体像)
あとは漢字。
頭で暗記はしているけど、
いざ書こうとすると書けない。
前回のテストで猪苗代湖が書けず、
今回は後醍醐天皇が書けず。
紙に書き出すアクティブリコール、
もっと取り組んだ方がいいかも。
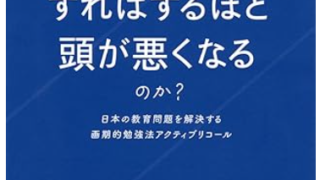
まとめ
国語と理科はよく頑張りました。
国語は記述問題が得点源になり、
偏差値70超の好成績。
理科も前回同様の好成績で、
小さな課題は気体の発生くらいかな。
・酸素が発生する場合は、気体の発生量が過酸化水素水の量で決まる
・水素や二酸化炭素の発生では、2種類の物質の過不足を考え気体の発生量を求める
算数と社会は課題が見つかりました。
特に算数は今回最も成績が悪く、
全体の足を引っ張ってしまう結果に。
凡ミスも目立ったし、
解けるハズの思考力問題も解けず。
凡ミスはコチラの本で対策するとして、
テスト対策を考えないとダメかも。

社会はテスト勉強量のわりに、
得点が伸び悩む結果に。
テキスト中心の勉強だけでは、
テストの細かな俊樹問題が解けない。
資料集や地図帳を読み込まないと、
細かな知識は身につかない。
今後はテキストだけでなく、
資料集や地図帳のテスト勉強も必須。
あと歴史用語は必ず、
漢字で書けるような勉強も必須。
・地理(ex 北朝/南朝の位置)
・建造物の特徴(ex 金閣寺の全体像)
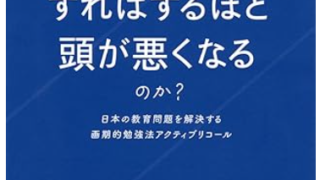
今回は残念ながら、
4科目で成績上位5%になれず。
算数さえ普段通りだったら、
と思うけど本番でも起こり得る。
ケアレスミスで取りこぼした点が、
合否を分ける点になるかもしれない。
ケアレスミスを防ぐよう、
普段の勉強から意識しないと。
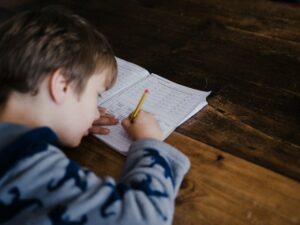
さて次回は、
12月度マンスリーテストですね。
今回の反省を活かして、
成績上位5%に返り咲けるか?
また次回書きますね。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)