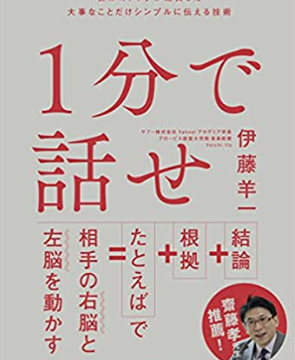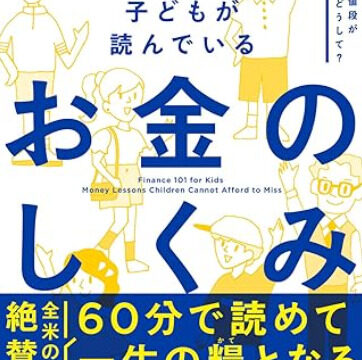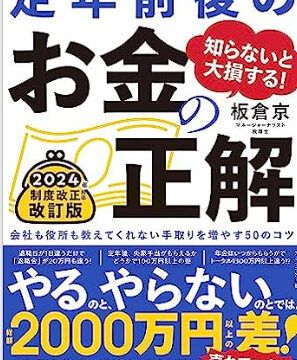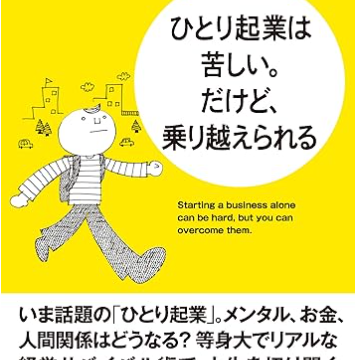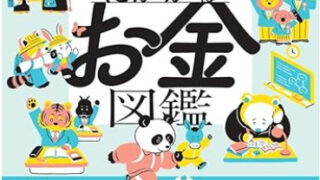【仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣】感想・レビュー
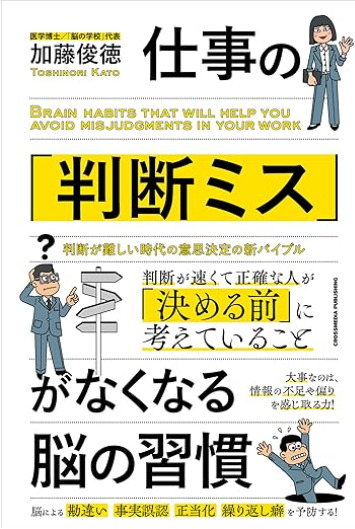
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
なぜ人は判断ミスを犯すのでしょうか?
「だって人間だもの みつを」
な~んて言ってると、
後で取り返しのつかないことに。。

小さな判断ミスで済めば、
些細な後悔で済むかもしれません。
でも大きな判断ミスは仕事を失い、
会社や人生を傾ける危険があります。
たとえば、
芸能人の不祥事を見ると、
判断ミスで引退に追い込まれる。
不祥事発覚時に即謝罪すれば、
復帰の可能性が後日あったのに。
二度と社会復帰できなくなったら、
困りますよね。

では、
どうすればいいでしょうか?
判断ミスをしなければいいけど、
人間だから難しいのでは?
でも、
致命的な判断ミスは避けたいよなぁ。
と思う方にオススメなのが、
コチラの本です。
判断ミスはなぜ起こるのか?
実は判断プロセスに問題が潜んでます。
一例を挙げるなら「思い込み」。
皆さんも一度は経験ありませんか?
「思い込み」によって疑うことを忘れ、
問題点に気づかず判断ミスをする。

このような判断ミスを防ぐには、
判断プロセスの仕組み化が必要です。
どんな判断プロセスを組めばよいか?
本書に書かれています。
判断プロセスを仕組み化すれば、
ある程度は判断ミスを防げます。

それでも完璧に防げないのが、
人間の限界でもある。
判断プロセスに慣れてくると、
馴れ合いになって安易に判断しがち。
その結果、
また判断ミスを犯すのです。

いつになっても判断ミスを防げない?
と思うかもしれませんが、
もう1つ対策があります。
だれでも簡単に、
しかも無料でできます。
後ほどご紹介しますね。

判断ミスを防ぎたい方は、
ぜひ本書をご覧ください。
判断ミスの原因と対策を学び、
より良い人生を送りましょう。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:なぜ「判断ミス」が起きるのか?
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・判断ミスに至るまでの4つの段階
<4つの段階>
①知覚・認知の段階
②感情・欲望の段階
③理解・記憶・分析の段階
④判断・選択・実行の段階
<判断ミスを防ぐ大事なポイント>
①対象に関する客観的な情報を、どれだけ収集することができるか
②理性を働かせ、情報をしっかり集める
③自分に都合の悪い情報に対して無関心だったり無視する
④過去の記憶や経験に縛られない
①~④が原因で、
判断ミスしたことありませんか?
人間が判断する以上、
①~④はどうしても起こりうる。
①~④を取り除いた判断をするには、
どうすれば良いか?
①先入観/思い込みで判断
②感情/欲望に任せて判断
③自分に都合の良い判断
④周りに同調して判断
そんな時は、
ChatGPTに聞くのが良いです。
自分なりの根拠と判断結果を、
ChatGPTに書く。
客観的に見てどう思うか?
判断ミスに可能性はないか?
他にどのような判断があり得るか?
ChatGPTなら、
無料でいくらでも相談に乗ってくれる。
他人に相談しても良いけど、
結局は人間の判断です。
①~④の影響はどうしても含まれるので、
参考程度にすると良いですね。

さて、
ChatGPTへの相談例を載せますね。
たとえば、
コチラの相談をしたとします。
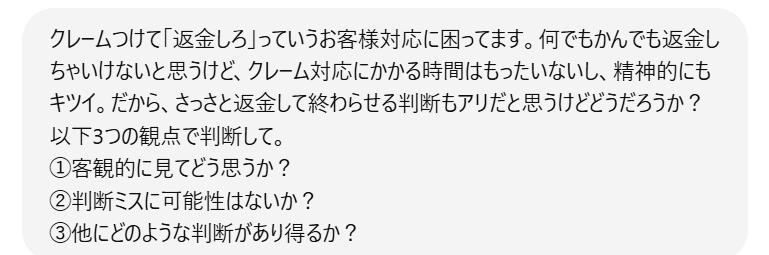
ChatGPTの回答はコチラ(↓)
返金or返金しない判断だけでなく、
一部返金/クーポン券等のアイデアも。
メリット/デメリットもわかるので、
判断材料になりますよね。
もし判断を相談したい場合、
ChatGPTを利用すると良いです。
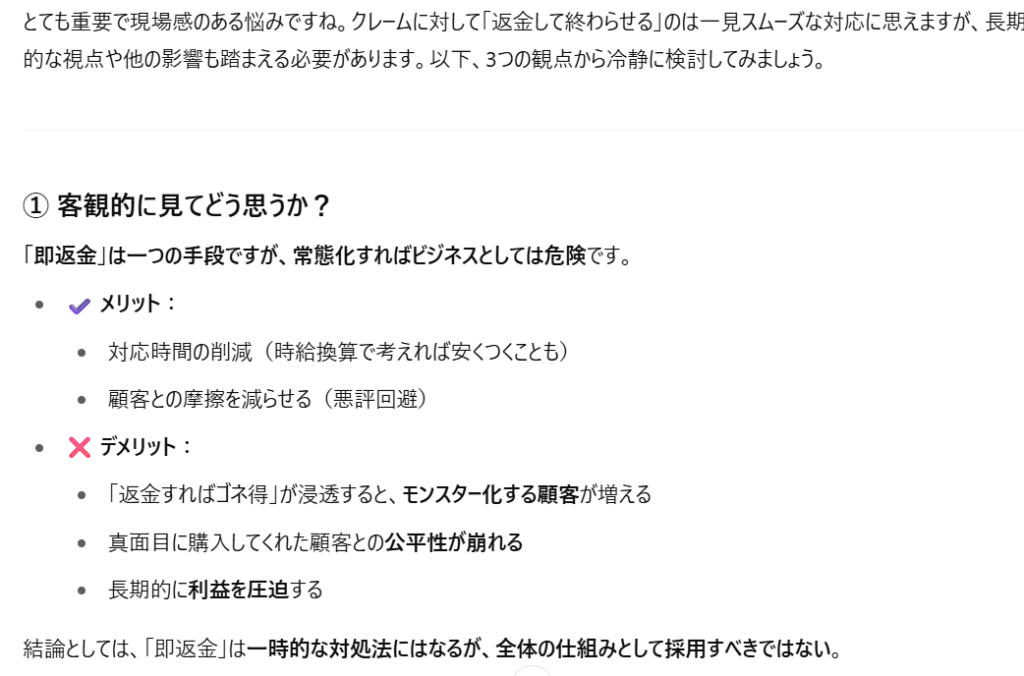
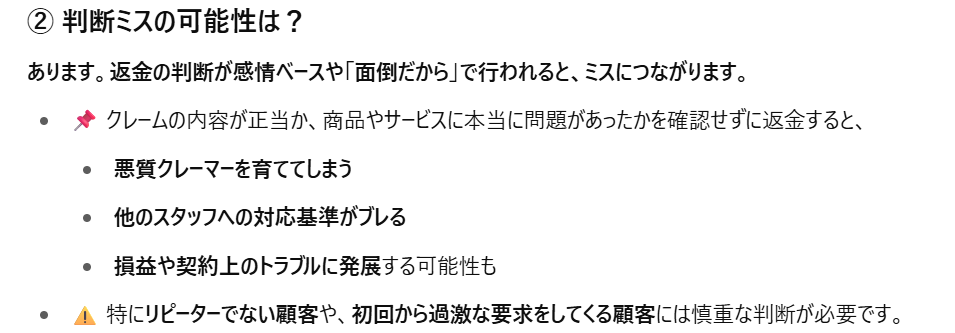
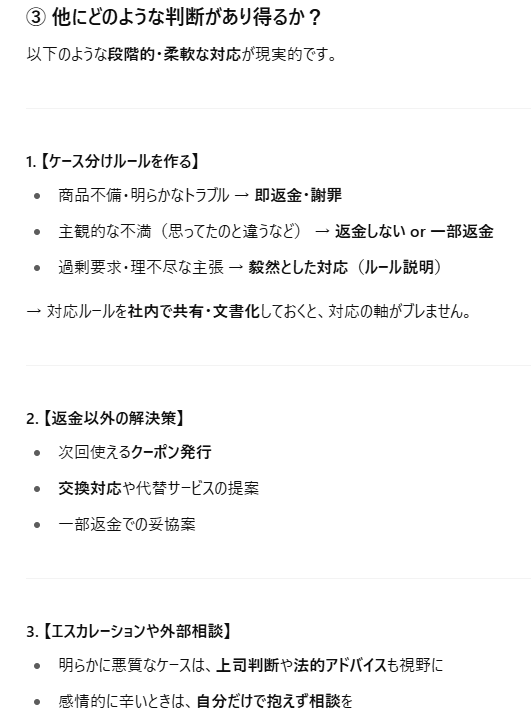
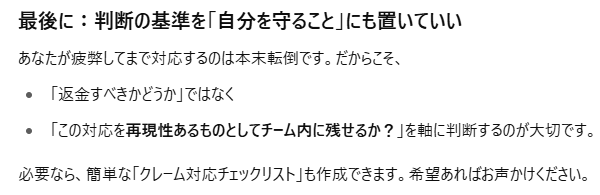
第2章:判断が正確な人は「逆算」して考えている
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・判断ミスのパターンを可視化する
ミスの原因を探り、
繰り返さないようにする。
失敗を減らすことが、
正確に判断する確率を上げる。
判断ミスの失敗事例を、
一か所にまとめればいいですね。
何かを判断する前に、
必ず失敗事例を振り返る仕組みを作る。
そうすれば、
判断ミスは自然と減りますね。
第3章:判断ミスを防ぐ「情報」の取り方
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・質のいい情報が自然と集まる状況を作る
<ポイント>
・一次情報をつねに得ようとする姿勢が大事になる
・他者から信頼されている人ほど、さまざまな有益な一次情報がもたらされやすい
・他者から見てわかりやすい人、表情が豊かな人、感情表現がストレートな人ほど、わかりやすい人物として信頼されやすい
一次情報とは何か?
自分が経験/体験したり、
調査/実験で得られた情報です。
つまり、
自分だけのオリジナル情報です。
ネット等の二次情報だと、
不明確な情報が多く判断ミスを招く。

どうすれば一次情報を得られるか?
本書に書かれているポイント以外に、
個人的に考える重要な要素があります。
それは、
あなた自身が一次情報を出すこと。
相手から一次情報をもらうのみでは、
相手から信用されないですよね。
いずれ一次情報が得られなくなる。
有益な一次情報を常にもらえれば、
判断ミスの可能性下がりますね。
第4章:直感が冴える!頭と体の使い方
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「直感」は脳の危機的反応から生まれてくる
<ポイント>
・脳科学的には、直感は脳の中の「偏桃体」「腹側線条体」「側坐核」と呼ばれる、感情や報酬に関与する部分が反応すると考えられている
・「偏桃体」は感情系脳番地の中枢であり、危険や危機的状況が生じたときに、瞬時に反応する部分です
・「腹側線条体」「側坐核」は過去の成功体験などを覚えている場所です
直感は突然生まれるのでなく、
豊富な経験値と情報から生まれる。
脳科学の知見を見ると、
直感が意外と当たるのも納得できます。
つまり、
直感はあながち間違いではない。
もちろん、
直感ばかりに頼るのはダメだけど。
直感は迷った時の最終判断基準、
くらいに考えると良いですね。
第5章:1日3分!判断力を磨く10の新習慣
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・何でも一度は疑ってみる
実際にやってみるとわかりますが、
結構難しいです。
いままでの常識を疑おうとしても、
疑問すら湧かないこともある。
何かを疑うより、
そのまま受け入れた方がラクだから。

では、
どうすればいいでしょうか?
ChatGPTを使うと、
簡単に疑うことができますね。
新たな判断の軸を知り得るので、
とても便利です。
たとえば、
ChatGPTにこう質問しました(↓)
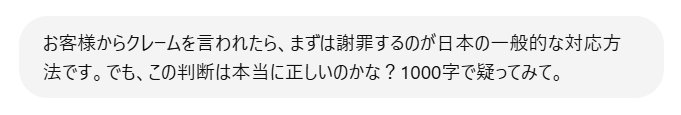
ChatGPTの回答はコチラ(↓)
謝罪よりも共感が大事、
という意見が出ましたね。
謝罪も大事だけど、
状況を見極め適切に対応するの大事、
と回答してます。
クレーム対応=謝罪という常識を疑うと、
このような判断もできるようになる。
ChatGPTは本当に便利なので、
ぜひご活用ください。
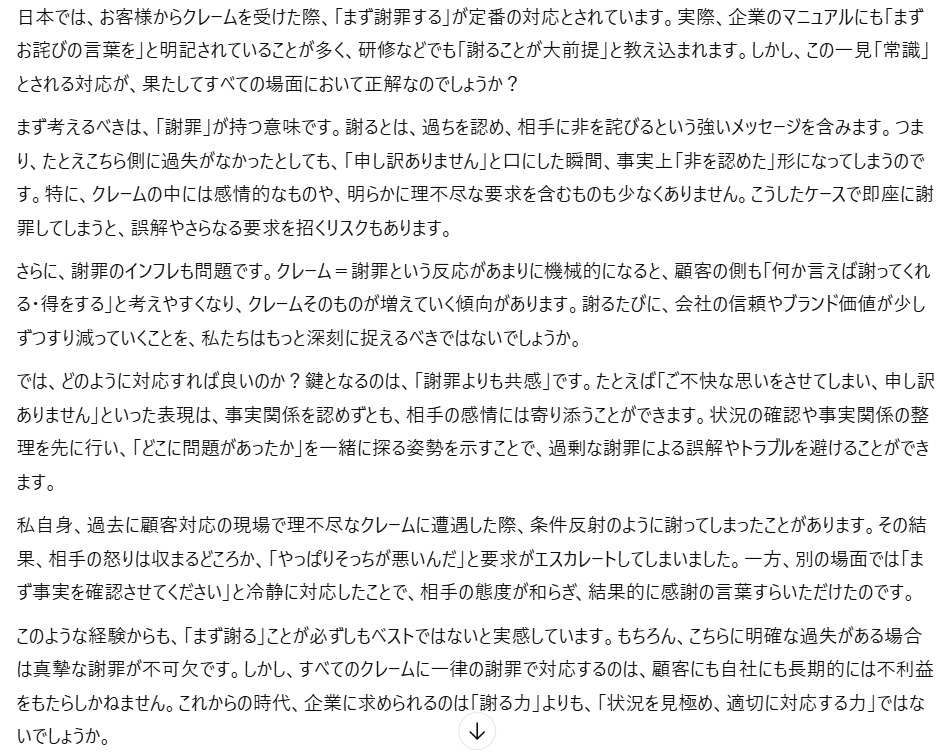
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:なぜ「判断ミス」が起きるのか?
・判断ミスに至るまでの4つの段階
<4つの段階>
①知覚・認知の段階
②感情・欲望の段階
③理解・記憶・分析の段階
④判断・選択・実行の段階
<判断ミスを防ぐ大事なポイント>
①対象に関する客観的な情報を、どれだけ収集することができるか
②理性を働かせ、情報をしっかり集める
③自分に都合の悪い情報に対して無関心だったり無視する
④過去の記憶や経験に縛られない
①先入観/思い込みで判断
②感情/欲望に任せて判断
③自分に都合の良い判断
④周りに同調して判断
第2章:判断が正確な人は「逆算」して考えている
・判断ミスのパターンを可視化する
第3章:判断ミスを防ぐ「情報」の取り方
・質のいい情報が自然と集まる状況を作る
<ポイント>
・一次情報をつねに得ようとする姿勢が大事になる
・他者から信頼されている人ほど、さまざまな有益な一次情報がもたらされやすい
・他者から見てわかりやすい人、表情が豊かな人、感情表現がストレートな人ほど、わかりやすい人物として信頼されやすい
第4章:直感が冴える!頭と体の使い方
・「直感」は脳の危機的反応から生まれてくる
<ポイント>
・脳科学的には、直感は脳の中の「偏桃体」「腹側線条体」「側坐核」と呼ばれる、感情や報酬に関与する部分が反応すると考えられている
・「偏桃体」は感情系脳番地の中枢であり、危険や危機的状況が生じたときに、瞬時に反応する部分です
・「腹側線条体」「側坐核」は過去の成功体験などを覚えている場所です
第5章:1日3分!判断力を磨く10の新習慣
・何でも一度は疑ってみる
まとめ
なぜ判断ミスが起こるのか?
どうすれば判断力を高められるのか?
多角的な視点から、
本書で解説されています。
判断ミスに至るのは、
4つの段階のどこかに原因がある。
判断ミスを防ぐには理性的に情報を集め、
不都合な情報にも耳を傾ける姿勢が必要。
①知覚・認知の段階
②感情・欲望の段階
③理解・記憶・分析の段階
④判断・選択・実行の段階
人間が判断する以上、
100%正しい判断をするのは難しい。
過去の判断ミスを可視化し、
次の判断に活かすのが現実的です。
過去の判断ミスを振り返り、
新たな判断ミスの確率を減らす。
これが正しい判断確率を上げることに、
つながるのです。

正しい判断をするには、
質の高い情報が不可欠です。
ネット等の不正確な二次情報ではなく、
自身の体験や調査から得た一次情報。
自分が信頼される人になり、
いかに一次情報を集められるか?
判断ミスをしないためには、
普段の心がけも大切なのです。

有益な一次情報を集めたとしても、
判断に迷うことはあるでしょう。
その場合は、
直感を信じるのもアリです。
直感は突発的に生まれるものではなく、
過去の経験や成功体験から生まれるもの。
迷ったときの補助的な判断基準として、
直感を活用するのが望ましいですね。

判断力を鍛えるのも大事だけど、
人間の判断力にはやはり限界がある。
直感を信じるのも不安ならば、
ChatGPTに判断してもらうのもアリ。
たとえば、
自分と違う判断をしてもらったり、
自分の判断を疑ってもらったり。
ChatGPTは使い方次第で、
人間には難しい判断も簡単にできる。
判断に迷う場合は、
ChatGPTをぜひご活用ください。

判断ミスにも大小あります。
小さなミスは大したことないけど、
大きなミスは致命傷となる。
仕事の大きな判断ミスは、
仕事や会社を失いかねない。
フジテレビを見ればわかるけど、
経営陣の判断ミスで大変な事態に。
1つの判断ミスが、
取り返しのつかない結果を生む。

さまざまな判断にお悩みの方は、
いますぐ本書を買い求めください。
判断ミスの原因や対応を学び、
判断ミスを事前に防ぎましょう。
判断ミスを起こさなければ、
あなたの悩みは軽減されますね。
ストレスがなくなり、
幸せな人生を送れるでしょう。
本書のお値段は1,738円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)