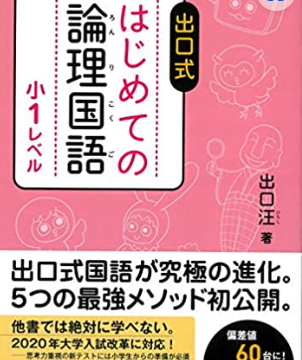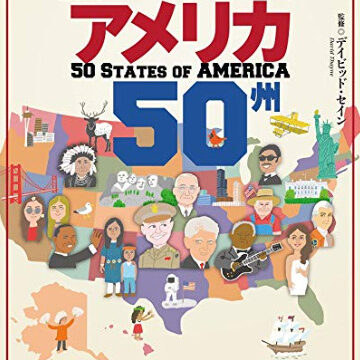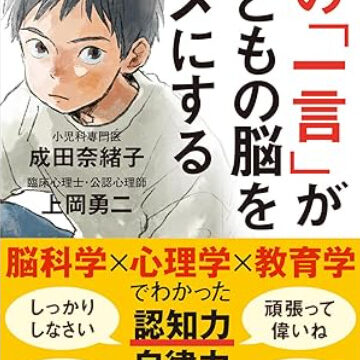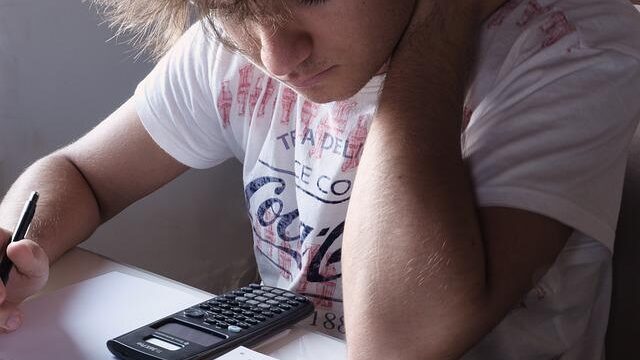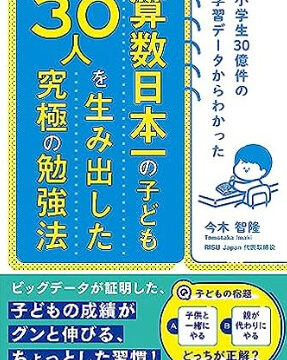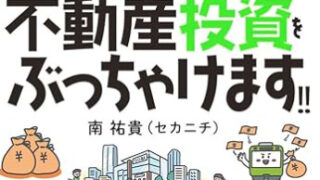【逆転合格東大生の受験お悩み相談】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
受験勉強で悩んだら、
だれに相談しますか?
友人/親/先生等が、
頭に思い浮かぶでしょうか。
でも、
意外と相談しにくいものです。

なぜか?
あまり知られたくない悩みなので。
友人に相談すると、
成績や志望校がバレてしまう。
親や先生に相談すると、
あれこれ口を出される。

それならAIに相談すればいい、
と思ったりもしますよね。
でも、
AIの回答は相談に乗ったものではない。
ChatGPTの仕組みはコチラ(↓)
質問に対する言葉の予測なのです。
・大量のテキストデータから単語間のつながりと関係性を学習している
・入力された文章の文脈を考慮し、次に来る可能性の高い単語を予測する
・単語を順番に並べていき、回答の作成を完了させる
コチラの本に書かれていますので、
ご興味あればぜひご覧ください。
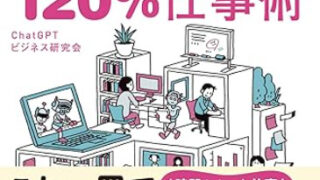
これでは誰にも相談できず、
受験の悩みが解消されないですよね。

では、
どうすればいいでしょうか?
受験本を読み、
悩みを解消すればいい。
でも、
どの本を読めばいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
浪人して東大に合格した著者が、
受験の悩みにQ&A形式で回答してます。
東大は受験界の最高峰であり、
さらに浪人経験もあるので、
Q&Aで参考になる箇所はあるハズです。
私の子どもは中学受験だけど、
浪人を除けば悩みはほぼ同じですよね。
実際に読んでみて、
中学受験でも参考になるなと感じました。
そのような箇所をまとめましたので、
ぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:受験や人生が不安なあなたに
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:どれだけ勉強しても、まだ足りないんじゃないかとずっと不安です
・A:勉強の目的設定が不足しているのです
<勉強の目的>
・インプットの勉強1:とりあえず結論だけ大雑把に早く理解したい
・インプットの勉強2:しっかりと基礎や途中の議論まで深く理解したい
・アウトプットの勉強1:とりあえず訓練を積んでインプットの理解を助けたい
・アウトプットの勉強2:しっかりと訓練を積んでテストで正解できるようになりたい
Qは子どもを見てると実感しますね。
SAPIXのテスト勉強、
どんなにやっても不安を口にする。
テスト範囲を一通りやったのだから、
不安になることないのに。

Qに対するAの考え方、
いままで意識したことなかったですね。
勉強目的の詳細は書かれてないけど、
子どものSAPIXに当てはめるとこう?
④過去の宿題を全部やる時間はないので、
間違った箇所を優先的にやりますね。
サピで成績上位5%をキープしてるので、
勉強の目的を教えて落ち着かせようかな。
<勉強の目的>
①インプットの勉強1:とりあえず結論だけ大雑把に早く理解したい
②インプットの勉強2:しっかりと基礎や途中の議論まで深く理解したい
③アウトプットの勉強1:とりあえず訓練を積んでインプットの理解を助けたい
④アウトプットの勉強2:しっかりと訓練を積んでテストで正解できるようになりたい
<SAPIXの勉強に当てはめると>
①授業を受ける
②宿題でテキストを精読する
③宿題で問題を解き授業の単元を理解する
④テスト範囲の問題を再度解く(過去の間違い箇所を中心に)
第2章:受験に向けた勉強習慣の作り方
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:スケジュールを立てて勉強しようと意気込んでも、なかなか計画通りにできません
・A:「何%まで達成すれば計画通りなのか」を考える
本書で興味深かったのは、
100%計画通りは逆に良くない点。
計画水準をもっと高くする必要がある、
という考えだそうです。
70~80%くらいが理想的かもしれない、
と著者は述べてますね。
つまり、
70~80%達成で計画通りと考える。

70~80%達成で計画通り、
いままで考えたことなかったですね。
仕事の進捗管理の感覚だと、
遅延に感じてしまう。
残りの20~30%をいつやって、
計画通りに戻すか?
こんな感じで考えていたけど、
勉強だから考え方を変えても良いかも。
仕事のように100%遂行で完成、
というわけでもないので。
SAPIXの宿題やテスト勉強計画で、
次回から実践してみます。
第3章:受験勉強の意味と勉強のコツ
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:数学の勉強、意味なくないですか?
・A:算数や数学を勉強しておかないと、基本的な思考力がない「察しが悪い人」になってしまうかもしれない
思考訓練の一環とも言える、
と本書に書かれていますね。
私もその通りだと思います。
途中式=論理的思考だと思うので。
たとえば、
子どもの算数で間違いがあるとします。
間違いの傾向として、
大きく2つに分かれます。
①途中式がそもそもおかしい
②途中式の考え方は合っているが、計算ミスをしている
②もったいないと思いつつも、
考え方は理解できてるなとわかる。
でも①が間違っていると、
根本から理解できていないとわかる。
①どう考えたのか子どもに聞いても、
おかしな理屈で説明してくる。
論理的におかしい箇所を指摘し、
子どもに解き直しをさせる。
これを繰り返すことで、
子どもは論理的思考力を身につける。

この論理的思考力、
社会人になると活きてきますね。
算数や数学が得意だった人は、
資料やプレゼンが論理的でわかりやすい。
具体的には、
定量的に書いたり話したりしますね。
逆に苦手な人はどちらもわかりにくい。
定性的な説明に終わることが多い。
仕事で評価されるのは、
数値を使って定量的に説明できる人です。
社会人になって仕事で苦労しないよう、
今から論理的思考力を身につけましょう。
第4章:後悔しない進路の決め方
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:そろそろ志望校を決めなさいと言われますが、どう決めればいいかわかりません
・A:実際に通える大学をさまざま条件から絞り込んで、そこから行きたい大学を決める方法が現実的です
本書は大学受験のQ&Aなので、
↓の条件が書かれてます。
①国立/私立
②家から通える範囲/下宿も視野に入れる
③理系/文系
中学受験の場合だと、
③はないけど①②は同じですね。
ただし、
②自宅通学の人が圧倒的に多いので、
通学時間はあらかじめ調べましょう。
個人的には、
片道1時間が目安ですね。
それ以上になると、
週6通うのは結構ハードです。

さて、
中学受験の志望校選びの場合、
偏差値で考える人もいますよね。
偏差値の指標だと、
このような絞り込み方法もある。
・偏差値(関東)=四谷大塚2024年入試結果
・偏差値(関西やその他)=日能研2024年入試結果
<最難関校(偏差値70以上)>
・塾のテキストの半分以上は自力で理解でき、塾のカリキュラムに乗った上で点数を出し、上位クラスにいられる
・公開テストも復習テストもそれなりの結果を出している
<難関校(偏差値60以上)>
・公開テストで正答率が70%以上の問題は基本的に落とさない
・復習テストに”自力”で対策をして臨んだ場合、7~8割は取る力がある
<中堅校(偏差値45以上)>
・範囲の決まっている復習テストは、”親や家庭教師の力を借りて”対策をして臨んだ場合、7割以上は取る力がある
<標準校(偏差値45未満)>
・小学校のカラーテストで7~8割取れている
コチラの本に書かれていますので、
ご興味あればぜひご覧ください。
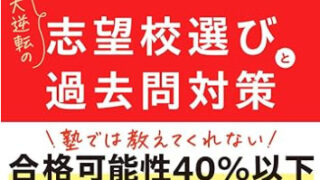
第5章:もし受験に失敗してしまったら
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:第2志望の大学に合格したけど、先生から「もう1年頑張ったらもうちょっといい大学に行けるよ」と言ってもらいました
・A:自分が納得できる道を選ぶしかありません
Aはその通りだと思いますが、
本章に興味深いデータがありました。
大学のランクごとに、
平均生涯年収が違うそうです。
具体的にはコチラ(↓)
・東大京大:4.5億円前後
・早慶:4億~4.5億円程度
・GMARCH、関関同立:3.5億~4億円程度
平均生涯年収だけなら、
浪人でワンランク上を目指すのもアリ。
中学受験で考えるならば、
大学附属校への進学目安でしょうか。
中学受験に浪人はないので、
ワンランク上を目指すなら大学受験か。
将来の収入だけで選ぶものじゃないけど、
もし迷った場合の目安ですね。
第6章:受験生の保護者が悩んでいること
第6章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・Q:背伸びしてレベルの高い高校を目指せるのと、自分の身の丈に合った高校を目指させるのとでは、どちらがいいと思いますか?
・A:背伸びした方がいい
Aの理由として、
周りの仲間の質と書かれてます。
これは私もその通りだな、
と思いますね。
人は良くも悪くも、
環境に左右されます。
質の高い仲間といる方が、
子どもは良い方向へ成長しますね。

ちなみに背伸びして合格すると、
入学後に↓で悩む人もいます。
・学習スピードが早すぎて勉強についていくのが大変
・テストでいい点が取れない
・精神的に悩んでしまう
その場合は落ち着いて、
生活リズムを取り戻しましょう。
環境の変化等で、
精神的に余裕がないだけかもしれない。
環境に慣れて精神的に落ち着けば、
学習スピードにも慣れてきます。
入学できたのだから、
学習スピードについていく学力はある。
コチラの本に書かれていますので、
ご興味あればぜひご覧ください。
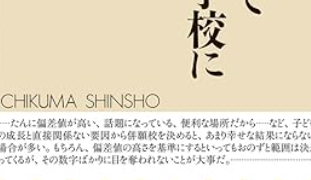
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:受験や人生が不安なあなたに
・Q:どれだけ勉強しても、まだ足りないんじゃないかとずっと不安です
・A:勉強の目的設定が不足しているのです
<勉強の目的>
・インプットの勉強1:とりあえず結論だけ大雑把に早く理解したい
・インプットの勉強2:しっかりと基礎や途中の議論まで深く理解したい
・アウトプットの勉強1:とりあえず訓練を積んでインプットの理解を助けたい
・アウトプットの勉強2:しっかりと訓練を積んでテストで正解できるようになりたい
<勉強の目的>
①インプットの勉強1:とりあえず結論だけ大雑把に早く理解したい
②インプットの勉強2:しっかりと基礎や途中の議論まで深く理解したい
③アウトプットの勉強1:とりあえず訓練を積んでインプットの理解を助けたい
④アウトプットの勉強2:しっかりと訓練を積んでテストで正解できるようになりたい
<SAPIXの勉強に当てはめると>
①授業を受ける
②宿題でテキストを精読する
③宿題で問題を解き授業の単元を理解する
④テスト範囲の問題を再度解く(過去の間違い箇所を中心に)
第2章:受験に向けた勉強習慣の作り方
・Q:スケジュールを立てて勉強しようと意気込んでも、なかなか計画通りにできません
・A:「何%まで達成すれば計画通りなのか」を考える
第3章:受験勉強の意味と勉強のコツ
・Q:数学の勉強、意味なくないですか?
・A:算数や数学を勉強しておかないと、基本的な思考力がない「察しが悪い人」になってしまうかもしれない
①途中式がそもそもおかしい
②途中式の考え方は合っているが、計算ミスをしている
第4章:後悔しない進路の決め方
・Q:そろそろ志望校を決めなさいと言われますが、どう決めればいいかわかりません
・A:実際に通える大学をさまざま条件から絞り込んで、そこから行きたい大学を決める方法が現実的です
①国立/私立
②家から通える範囲/下宿も視野に入れる
③理系/文系
・偏差値(関東)=四谷大塚2024年入試結果
・偏差値(関西やその他)=日能研2024年入試結果
<最難関校(偏差値70以上)>
・塾のテキストの半分以上は自力で理解でき、塾のカリキュラムに乗った上で点数を出し、上位クラスにいられる
・公開テストも復習テストもそれなりの結果を出している
<難関校(偏差値60以上)>
・公開テストで正答率が70%以上の問題は基本的に落とさない
・復習テストに”自力”で対策をして臨んだ場合、7~8割は取る力がある
<中堅校(偏差値45以上)>
・範囲の決まっている復習テストは、”親や家庭教師の力を借りて”対策をして臨んだ場合、7割以上は取る力がある
<標準校(偏差値45未満)>
・小学校のカラーテストで7~8割取れている
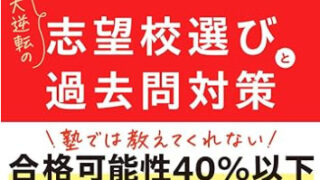
第5章:もし受験に失敗してしまったら
・Q:第2志望の大学に合格したけど、先生から「もう1年頑張ったらもうちょっといい大学に行けるよ」と言ってもらいました
・A:自分が納得できる道を選ぶしかありません
・東大京大:4.5億円前後
・早慶:4億~4.5億円程度
・GMARCH、関関同立:3.5億~4億円程度
第6章:受験生の保護者が悩んでいること
・Q:背伸びしてレベルの高い高校を目指せるのと、自分の身の丈に合った高校を目指させるのとでは、どちらがいいと思いますか?
・A:背伸びした方がいい
・学習スピードが早すぎて勉強についていくのが大変
・テストでいい点が取れない
・精神的に悩んでしまう
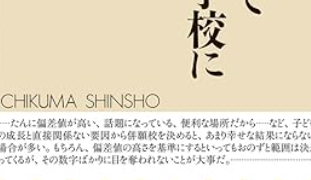
まとめ
本書は大学受験のQ&Aだけど、
中学受験でも役立ちます。
第5章以外で例に挙げた箇所、
中学受験も大学受験も同じですよね。
・第1章:勉強に不安を抱える
・第2章:勉強スケジュールを立てる
・第3章:算数/数学を勉強する意味
・第4章:志望校の決め方
・第6章:どちらに進学?(レベルの高い学校or身の丈に合った学校)
第5章だけ少し違いますね、
中学受験は不合格でも、
公立中学に進学できます。
大学受験で不合格だと、
浪人という選択肢があります。
でも中学受験する場合、
いずれ大学受験もされますよね?
今すぐでなくても、
参考になる箇所かなとは思います。

受験とはマラソンのようなものです。
受験本番まで先が長いので、
途中で不安になってもおかしくない。
逆に何の不安もなく受験する人、
おそらくいないですよね。

受験の悩みって、
意外と周りに相談しにくいものです。
親や先生に相談すれば、
あれこれ言われてめんどくさい。
同級生に相談すれば、
成績や志望校がバレてめんどくさい。
でもだれかに相談しないと、
受験の悩みは解消しない。

受験でお悩みの方は
いますぐ本書をお買い求めください。
本書には数多くの悩みに対して、
東大生ならではの回答が載っています。
実際に読んでみましたが、
いろいろと参考になることが多い。
大学受験用の本ですが、
中学受験でも参考になりますね。
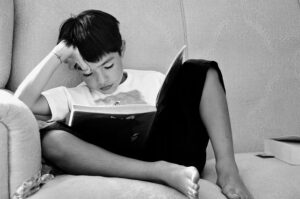
受験の悩みを解消しないと、
受験勉強に本腰入らないですよね。
そんな状態で受験しても、
合格する可能性は低い。
きちんと悩みを解消し、
目的をもって受験勉強しましょう。
本書に書かれたことを実践すれば、
きっと合格に近づきますね。
受験でお悩みの方は、
いますぐ本書をお買い求めください。
本書のお値段は1,375円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)