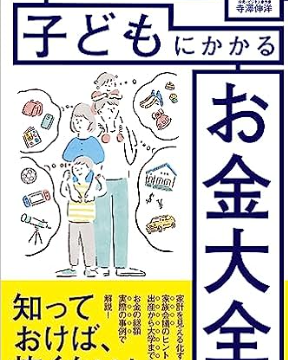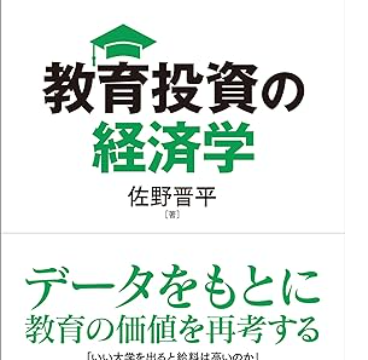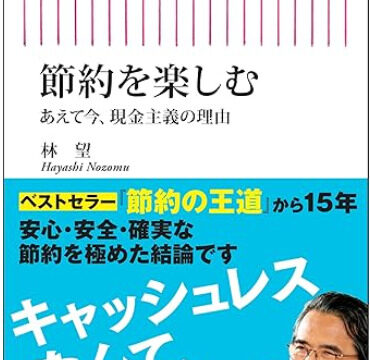【再雇用という働き方 ミドルシニアのキャリア戦略】感想・レビュー
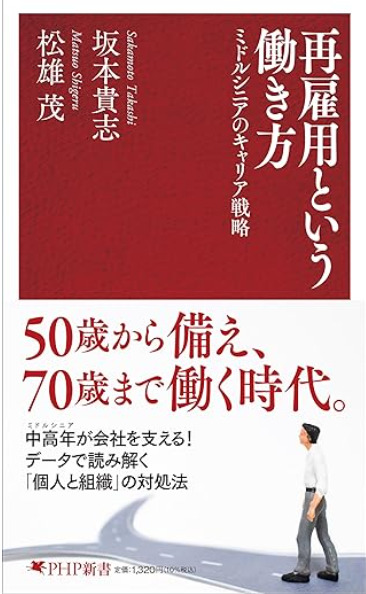
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
定年を迎えたら、
あなたはどう働きますか?
再雇用で65歳まで働く、
と考える人は多いでしょう。
再雇用は60歳で退職金を受け取り、
その後は契約社員として1年更新で働く。
表向きは雇用の安定が保障されてるけど、
待遇低下や不安定な働き方があるのです。
この現実を直視せずに定年を迎えた場合、
想定外の収入減や役割喪失に直面します。

特に管理職を経験してきた人ほど、
役職を外されるショックは大きい。
メンタルを崩してしまうケースも、
少なくありません。
さらに、
定年後の収入は平均して2割減。
住宅ローンや教育費が残っていれば、
生活は一気に苦しくなります。
老後の資金不足に気づいても、
その時には取り返しがつかないのです。

では、
どうすればいいでしょうか?
定年後の働き方に備えて、
いまから準備するしかないです。
でも、
何をどうやって準備すればいいの?
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
お金の準備として、
資産形成や支出削減を行う。
さらに気持ちの準備として、
役職定年後の自分を想定する。
そして役職定年後の準備として、
プレーヤーとして働ける練習をする。
大枠はこんな感じですが、
きちんと準備している人は意外と少ない。
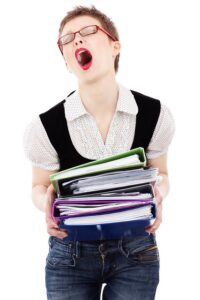
私も過去に、
いろいろな人を見てきました。
役職定年後に給与が下がったけど、
住宅ローンや教育費に悩む人。
役職定年でモチベーションが下がり、
職場に悪影響を与えた人。
再びプレーヤーとして輝けず、
退職してしまった人。

このような人生になってしまうと、
老後までの生活すら怪しくなる。
何とか乗り越えたとしても、
老後は苦しい年金生活になる。
もしあなたが40代以上なら、
今後に一抹の不安を抱えていませんか?
もし不安を抱えているなら、
ぜひ本書をご覧ください。
備えあれば憂いなし。
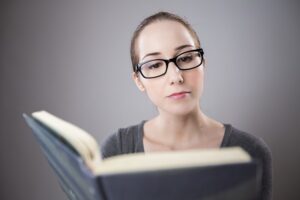
それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:高齢期キャリアの構造
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・定年後の働き方は「再雇用」が半数以上
<ポイント>
①2025年4月に改正高年齢雇用安定法が施行され、希望者全員の65歳までの雇用が完全に義務化された
②再雇用制度とは定年を迎えた社員を一度退職させ、退職金を支払い、新たに雇用契約を結ぶ制度である
③勤務延長生徒は、定年に達した社員を退職させることなく、引き続き雇用する制度である
一番多いのは②ですね。
60歳以上の雇用制度の実態を見ると、
②が約60%を占めています。
定年退職後は1年ごとに契約更新を行う、
有期の契約社員が多いですね。

私の周りを見ていると、
定年後も契約社員で働くものの、
65歳より前に退職する人が多いです。
65歳から年金をもらえるので、
数年は貯蓄取り崩しで生活してますね。
投資で十分な資産があれば、
定年後に働く必要もない。
自分の資産と年金までの年数を踏まえ、
何歳まで働くかを考えると良いかも。
第2章:過渡期の継続雇用
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・若手従業員が減少する中、プレイヤーが不足へ
<ポイント>
・2024年の年齢層の一番の山は45~54歳である
・2024年の25~34歳は1061万人に対して、45~54歳は1404万人と大きく上回っている
・若手従業員の採用が困難になる中で、企業人事は若手従業員の定着に頭を悩ませている
若手従業員が足りないのは、
中高年にとって逆にチャンスでは?
もし管理職になれなくても、
プレイヤーとして生き残れるから。
一部の業務はAI化されるとしても、
すべての業務がAI化されるのはまだ先。
もしAIに強い中高年になれば、
若手不足を補える貴重な戦力になる。
むしろ管理職しかできない人の方が、
将来厳しいのでは?と思ったりしますね。
第3章:働く社員が直面する家計と意識の構造変化
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・大企業では3割、中小企業では1割の年収減
<ポイント>
・定年前に正規雇用者であった人の定年後の年収は、約21.1%減少となっている
・ホワイトカラーで管理職として働いていた人は、大きく収入が減少する傾向がある
・現場に近い人手不足の職種で仕事をしている人は、定年後もそれほそ収入水準が変わらない傾向がある
自分の年収から約2割減る想定で、
人生設計を考えた方がいいです。
収入が2割減でも生活できるか?
これがポイントです。
たとえば、
定年までに住宅ローンを完済し、
教育費が終わっていないと厳しい。

もし生活が厳しくなるなら、
いまから準備しておいた方がいい。
大きな支出を減らすのも大事だし、
資産運用でお金を増やすのも大事。
1800万まで非課税で運用できるし、
イザと言う時に取り崩しもできる。
コチラの本がわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。

第4章:悩ましい年下上司との関係
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・ミドルシニア社員の複雑な感情
<複雑な感情>
・自分にはもう昇進・昇格のチャンスはないだろう
・自分より若い後輩が次々に管理職に昇格していく
・重要な仕事、新しい仕事は優先的に若手にチャンスが与えられる
・仕事の各論で関われることは少ない
・上司も自分に遠慮している。あまりはっきり言わない
・今さら会社を辞める勇気も自信もない
・まだ家族のために働かなくてはならない
遅かれ早かれ、
多くの人が直面する気はします。
昇進できなかった人は、
かなり早い段階からこの感情を抱く。
でも徐々に抱く感情なので、
徐々に折り合いもつけやすい。

ポストオフされる人の方が、
キツイ気はしますね。
事前にわかっていても、
複雑な感情と折り合えない。
ポストオフの年齢にもよるけど、
50代中盤だとキツイですよね。
昇進するか否かに関係なく、
心の準備はしておいた方がいいですね。
メンタルを病んで休職→退職しないよう、
ご注意ください。
第5章:人事制度改革の方向性-再雇用制度化、定年延長制度か
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・部長・課長はどのようなプロセスで役職を降りるのか
<ポイント>
①役職定年した後は、概ね同格の専門職につくケースもある
②同格の専門職につくと役職手当は無くなるが、基本給を大きく下げると大きな影響が生じるため、給与を過度に下げないため措置が取られる
③同格の専門職でいられる期間は長くない
③概ね2~3年のようです。
第4章でも書いたけど、
ポストオフは結構キツイです。
特に部長からのポストオフはキツイ。
プレーヤーへ簡単に戻れないから。
プレーヤーから離れた期間が長いほど、
戻っても昔のように活躍できない。
部長→プレーヤーに戻った人を見たけど、
活躍できたのはほんの一握りの印象。

課長からポストオフの方が、
まだ現場に戻りやすいですね。
プレイングマネジャーも多いので、
プレーヤーの感覚がまだ残ってます。
プレーヤーの割合が少ない課長ほど、
プレーヤーに戻った時はキツイ。
いつかプレーヤーに戻ることを想定し、
少しは手を動かしておく方が良いですね。
第6章:70歳雇用時代に向けた処方
第6章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・選択肢を見つめ、準備を始める
<ポイント>
・お金:年金や継続雇用後の給与水準、子どもの教育費や住宅ローンの残債などの詳細なシミュレーションを行う
・気持ち:組織内で役職に就き続けられる淡い期待を断ち切り、ポストオフを覚悟する
・準備:職業人生の終盤は管理職を離れることを前提として、その後に向けて準備を始める
第1章~第5章で書いた内容の、
まとめですね。
お金を計算し、
気持ちの整理を行い、
ポストオフ後の準備をする。
定年までこのまま働ける、
と漠然と考える人が多すぎます。
会社はそんなに甘くないし、
若くて給料が安い人を使いたい。
そんな現実を踏まえて、
いまから準備した方がよいですね。
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:高齢期キャリアの構造
・定年後の働き方は「再雇用」が半数以上
<ポイント>
①2025年4月に改正高年齢雇用安定法が施行され、希望者全員の65歳までの雇用が完全に義務化された
②再雇用制度とは定年を迎えた社員を一度退職させ、退職金を支払い、新たに雇用契約を結ぶ制度である
③勤務延長生徒は、定年に達した社員を退職させることなく、引き続き雇用する制度である
第2章:過渡期の継続雇用
・若手従業員が減少する中、プレイヤーが不足へ
<ポイント>
・2024年の年齢層の一番の山は45~54歳である
・2024年の25~34歳は1061万人に対して、45~54歳は1404万人と大きく上回っている
・若手従業員の採用が困難になる中で、企業人事は若手従業員の定着に頭を悩ませている
第3章:働く社員が直面する家計と意識の構造変化
・大企業では3割、中小企業では1割の年収減
<ポイント>
・定年前に正規雇用者であった人の定年後の年収は、約21.1%減少となっている
・ホワイトカラーで管理職として働いていた人は、大きく収入が減少する傾向がある
・現場に近い人手不足の職種で仕事をしている人は、定年後もそれほそ収入水準が変わらない傾向がある

第4章:悩ましい年下上司との関係
・ミドルシニア社員の複雑な感情
<複雑な感情>
・自分にはもう昇進・昇格のチャンスはないだろう
・自分より若い後輩が次々に管理職に昇格していく
・重要な仕事、新しい仕事は優先的に若手にチャンスが与えられる
・仕事の各論で関われることは少ない
・上司も自分に遠慮している。あまりはっきり言わない
・今さら会社を辞める勇気も自信もない
・まだ家族のために働かなくてはならない
第5章:人事制度改革の方向性-再雇用制度化、定年延長制度か
・部長・課長はどのようなプロセスで役職を降りるのか
<ポイント>
①役職定年した後は、概ね同格の専門職につくケースもある
②同格の専門職につくと役職手当は無くなるが、基本給を大きく下げると大きな影響が生じるため、給与を過度に下げないため措置が取られる
③同格の専門職でいられる期間は長くない
第6章:70歳雇用時代に向けた処方
・選択肢を見つめ、準備を始める
<ポイント>
・お金:年金や継続雇用後の給与水準、子どもの教育費や住宅ローンの残債などの詳細なシミュレーションを行う
・気持ち:組織内で役職に就き続けられる淡い期待を断ち切り、ポストオフを覚悟する
・準備:職業人生の終盤は管理職を離れることを前提として、その後に向けて準備を始める
まとめ
2025年4月施行の改正高年齢雇用安定法により、
希望者全員が65歳まで雇用を義務化されました。
その中心は再雇用制度で、
定年後に退職し再契約する形です。
定年後に再雇用で働くものの、
65歳を待たず退職する人も少なくない。
年金や資産状況を踏まえ、
何歳まで働くのか考える人が多い。
定年後の年収は約2割下がるので、
早めの資産形成や支出削減が必須です。

企業がシニアを活用する背景には、
若手人材の不足があります。
数少ない若手を採用するのは難しく、
採用できてもすぐ転職してしまう。
これは中高年にとってむしろチャンス。
プレーヤーとしての活躍の場は残るので。
管理職に昇進できない方が、
むしろ生き残るチャンスはある気もする。

管理職の人は、
むしろポストオフにご注意ください。
だれもが定年まで、
役職をキープできるわけじゃない。
特に部長→プレーヤーは戻りにくい。
プレーヤーから離れすぎてるので。
給与削減幅も大きいので、
気持ちの整理もなかなか難しい。
管理職であっても、
プレーヤーのスキルを磨いておくと良い。

私の周りを見ていると、
意外と準備していない人が多いです。
なんとなくこのまま定年を迎えるのかな、
と漠然と考える人が多い。
そんな人ほどポストオフや再雇用になり、
モチベーションが下がり戦力にならない。
その先に待っているのは、
こんなハズじゃなかったという思いだけ。

その時に後悔してももう遅い。
資金面で不安を抱えても、
だれも助けてくれない。
管理職であろうとなかろうと、
いまから将来に備えて準備するのみ。
その準備の仕方は、
本書に詳しく書かれています。
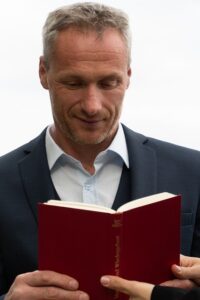
今後に不安を覚える40代以上の方。
いますぐ本書をお買い求めください。
本書に書かれたことを実践し、
シニアのキャリアを構築しましょう。
そうすれば充実した現役生活を送り、
幸せな老後生活を迎えられますね。
本書のお値段は1,320円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)