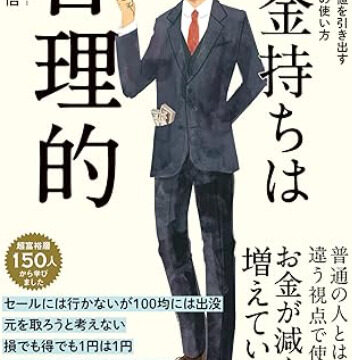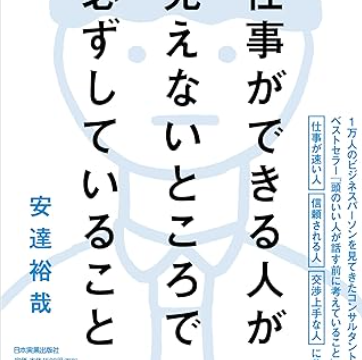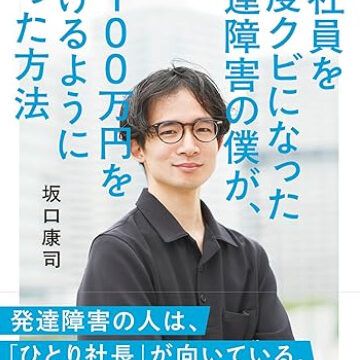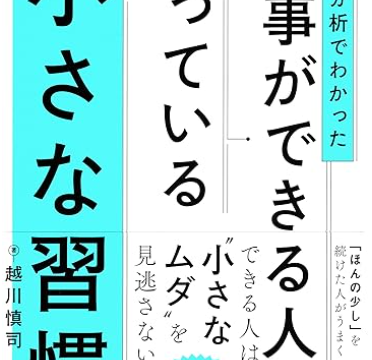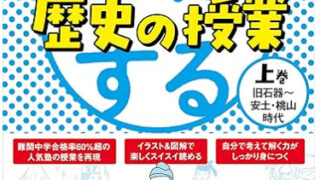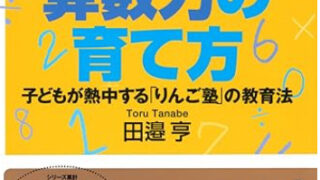【お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点】感想・レビュー
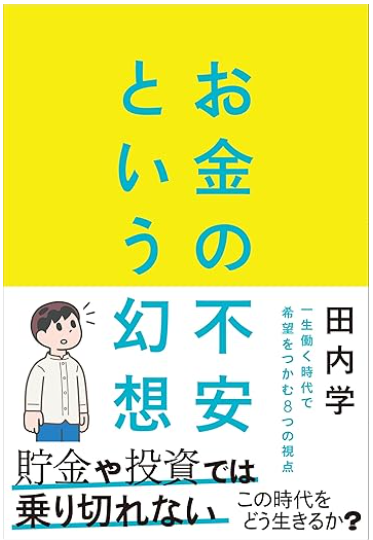
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』
「老後2,000万円が足りない」
金融庁レポートが世間を騒がせ、
多くの人が老後資金へ不安を抱きました。
年金では足りない。
貯金でも足りない。
投資でお金を増やさないと。
若者ならこの先いくらでも稼げるし、
長期投資も可能なので不安は少ない。
でも老後がチラつく世代になると、
この先の稼ぎや投資期間も限られる。
老後資金をどうすべきだろうか。。
ちょっと待った!
お金の不安に過剰反応しすぎでは?

なぜか?
お金はあるに越したことないけど、
ないなりに備える手段はあるからです。
具体的にどんな手段?
コチラの本が参考になります。
『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』
投資で備えるのは1つの手段であり、
他にも手段はあります。
老後に働くのも1つの選択肢だし、
周りの支援を受ける方法もある。
お金のことばかり考えてしまうと、
不安のループから抜け出せなくなる。
さまざまな知恵があれば、
不安ビジネスの罠から抜け出せる。
お金の不安を抱えている方は、
ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
- 1 第1話:その不安は誰かのビジネス-焦りを生む空気からどう抜け出すのか?
- 2 第2話:投資とギャンブルの境界線-成功者を真似てもなぜうまくいかないのか?
- 3 第3話:「会社に守られる」という幻想-労働と投資、報われるのはどちらか?
- 4 第4話:愛と仲間とお金の勢力図-お金以外の何を頼ればいいか?-お金以外の何に頼ればいいか?
- 5 第5話:「あなたのせい」にされた人口問題-なぜ「稼ぐ人が偉い」と思われるのか?
- 6 第6話:「お金さえあれば」の終焉-いつまでお金に支配されるのか?
- 7 第7話:「仕事を奪う」が投資の出発点-どうすれば仕事を減らせるのか?
- 8 第8話:「子どもの絶望」に見えた希望-”大人”の常識はこれからも通用するか?
- 9 まとめ
- 9.1 第1話:その不安は誰かのビジネス-焦りを生む空気からどう抜け出すのか?
- 9.2 第2話:投資とギャンブルの境界線-成功者を真似てもなぜうまくいかないのか?
- 9.3 第3話:「会社に守られる」という幻想-労働と投資、報われるのはどちらか?
- 9.4 第4話:愛と仲間とお金の勢力図-お金以外の何を頼ればいいか?-お金以外の何に頼ればいいか?
- 9.5 第5話:「あなたのせい」にされた人口問題-なぜ「稼ぐ人が偉い」と思われるのか?
- 9.6 第6話:「お金さえあれば」の終焉-いつまでお金に支配されるのか?
- 9.7 第7話:「仕事を奪う」が投資の出発点-どうすれば仕事を減らせるのか?
- 9.8 第8話:「子どもの絶望」に見えた希望-”大人”の常識はこれからも通用するか?
- 9.9 まとめ
第1話:その不安は誰かのビジネス-焦りを生む空気からどう抜け出すのか?
第1話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・カネも不安も売る時代
<ポイント>
①2019年、「老後資金が2000万円不足する」という金融庁のレポートが話題になった
②老後の不安なら、地域や家族との支え合いという方法もあるし、定年後も働けるスキルを身につける選択肢だってある
③不安を感じる私たちに金融機関が忍び寄る
②は一理あるけど、
私はどうかなと思う一面もある。
地域や家族が支え合うとは限らないし、
定年後に働ける保証もない。
仮にスキルがあったとしても、
身体にガタが来たら働けない。
老体に鞭打って働く高齢者を見ると、
自分はこうなりたくないなと思う。

不安を煽って商品を買わせるのは、
ある意味でビジネスの基本ですね。
ビジネスではニード喚起と言います。
やり過ぎはもちろんダメだけど。
老後2000万円の問題は、
余裕資産があれば不安にならずに済む。
どう資産形成するかが問題であり、
投資以外の方法でできるなら何でもいい。
新NISAの限度額1800万を運用できれば、
個人的には問題ないと思うけど。
新NISAはコチラがわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。

第2話:投資とギャンブルの境界線-成功者を真似てもなぜうまくいかないのか?
第2話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・健全な投資とギャンブルの見分け方
<ポイント>
①投資の健全性を見極めるシンプルな質問「その利益は、誰の役に立った報酬なのか?」
②値上がり益ばかりを強調する投資は、「自分より高く買ってくれる誰か」が現れなければ成立しない
③他人の財布を狙うということは、あなたの財布も誰かに狙われているということだ
的を得ている見分け方ですね。
①が答えられない投資は、
ギャンブル要素が強いってことです。
たとえば、
FXや仮想通貨(暗号資産)。
だれの役に立っていますか?

①を満たす投資例、
本書に書かれているのはコチラ(↓)
株式投資と不動産投資には、
①だけでなく②の要素もあります。
短期投資に走る投資家ほど、
②の要素が強くなる傾向にあります。
ギャンブル要素が強くなるので、
あまりオススメしないです。
<①誰かの役に立った報酬+他の投資家をあてにしたお金>
・株式投資:①配当+②売却益(or売却損)
・不動産投資:①家賃+②売却益(or売却損)
・預金:①利息のみ
ただし②でも例外はある、
と個人的には思いますね。
たとえば、
株や不動産を長期保有後に売却のケース。
株式市場は長期的には右肩上がりなので、
長期投資すればギャンブル要素は減る。
不動産も長く住んだ後に売却なら、
新たな住人のためになる。
売却資金を老後資金に充てるのは、
理に適ってますね。
第3話:「会社に守られる」という幻想-労働と投資、報われるのはどちらか?
第3話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「稼ぐ力」の磨き方-仕事から「為事」へ
<ポイント>
・本来、働くこととは、誰かに仕えることではなく、自分の力で価値を生み出すことだ
・長らく社会では、「役に立つこと」と「稼ぐこと」が分断されていた
・人手不足や安泰神話の崩壊を背景に、「役に立つこと」をすれば「稼ぐこと」につながる社会に戻りつつある
人口減による人手不足、
ある意味でチャンスに感じます。
人口増の社会では、
言葉は悪いけど代わりはいくらでもいた。
でも、
人口減の社会では、
代わりが見つからずに困る企業が多い。
時給を上げても採用できず、
人材難に悩む企業が増えてますよね。

企業が人材難に悩めば、
サービスも滞ります。
ここであなたが企業の代わりに、
サービスを提供できれば稼げるのです。
たとえば保育でも介護でも、
人材不足の業界はたくさんあります。
為事はいくらでもあるので、
会社に縛られず稼ぐに困らない時代。
終身雇用の方がいいという人もいるけど、
いまの時代もけっして悪くないですよ。
第4話:愛と仲間とお金の勢力図-お金以外の何を頼ればいいか?-お金以外の何に頼ればいいか?
第4話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「不安」と「ゴール」の共有戦略
<ポイント>
①「お金の不安」は個人的すぎて共有しにくい
②自分の問題が解決しても、周囲には妬みや距離感が生まれることがある
③学生時代、「社会のために働く」という言葉を「きれいごとだ」と思っていたが、今ではそれが孤立を防ぎ、仲間とつながるための戦略でもあったとわかる
その通りだなと感じますね。
私が一番避けたいと思っているのは、
③孤立です。
孤立は健康を損ない、
孤独死を招く可能性があるからです。
いくら①②お金があっても、
仲間がいない生活は寂しいです。

私は友人関係を大事にしてます。
けっして多くはないけれど、
信頼できる友人と年に数回会う。
これだけでも孤独を感じずに済むし、
自分への刺激にもなる。
プライベートの人間関係は、
大事にした方がいいと思いますね。
第5話:「あなたのせい」にされた人口問題-なぜ「稼ぐ人が偉い」と思われるのか?
第5話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・値上げされた100円は、どこへ消えた?
<ポイント>
・2022年以降、電気代や建築費やうどんのねだんまでが上昇したが、給料はなかなか追いついてこない
・うどんの値上げ分の100円は国内ではなく、海外の生産者の収入となっている
・値上げされた100円は必ず誰かの収入になるが、問題はそのお金が海外に流出していく構造にある
うどんの値上げ例を挙げたけど
他の値上げも同じ構図です。
日本は原材料の多くを輸入に頼っており、
お金が海外流出する要因となっている。
日本は人口減なので、
国内生産が不足すれば輸入がさらに増す。
お金が海外に流出する要因が増え、
給料は上がりにくくなる。
この傾向は今後も変わらないでしょうね。

いまの日本は、
実質賃金が低下しています。
給料も少しは増えているけど、
それ以上に物価高で実質マイナス。
私は円安ドル高を活かして、
海外投資で補っています。
海外は経済成長してますので、
長期投資でドル資産を増やす感じ。
海外投資はコチラがわかりやすいので、
ご興味あればぜひご覧ください。
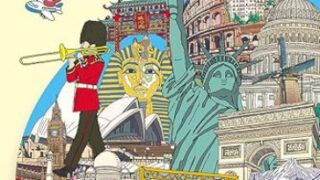
第6話:「お金さえあれば」の終焉-いつまでお金に支配されるのか?
第6話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・経済を回せない巨大ピラミッドの罠
<ポイント>
①重要なのは「何に使うか」ではなく、「どれだけ使うか」。経済効果やGDPという数字が、その考えを裏付ける指標としてもてはやされた
②しかし、この考えの前提にあるのは、ヒトもモノも豊富に存在していることだ
③「お金さえ回せば経済はよくなる」という常識は、ヒトもモノも無限に存在するという前提に立った、旧世界の幻想にすぎない
日本が景気低迷から抜け出せないのは、
人口減の影響が大きいです。
かつては人口増の社会だったので、
①~③のやり方で経済成長できました。
しかしいまは人口減です。
預貯金や企業の自社株買いを見る限り、
カネ余りで回す先がない。

人口減社会のモデルが過去になく、
右往左往しているように見えます。
理想は人口増の社会だけど、
少子化は解決の糸口が見えない。
そうなると、
人口減を前提にした社会構造に、
変換する時期なのかもしれませんね。
人口減を補うほどITが進化するのか?
まだわからないですね。
第7話:「仕事を奪う」が投資の出発点-どうすれば仕事を減らせるのか?
第7話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「シイタケ」で読み解く給料アップの秘密
<ポイント>
①長い目で見ると私たちの生活は確実に豊かになった
②1920年から2020年の100年間で、食費は2280倍に上昇したが、給料は5000倍に増えた
③今スーパーで1パック400円のシイタケの値段は、100年前の感覚なら5000円もする高級品だ
①②だけ見ると豊かに思えるけど、
直近数年は違いますよね。
給料の伸びより、
食費の伸びの方が上回ってます。
実質賃金が減っているので、
投資等で補わないとお金は減っている。

③なぜ劇的に安くなったのか?
栽培技術が劇的に進化したからです。
本書の例を書くと、
100人で山に入って収穫する状況から、
8人で生産できるようになった感じ。
つまり、
効率化によって仕事を減らした時に、
給料が物価以上に上がるそうです。
いまの時代だと、
効率化のキーになりそうなのはAI?
人口減の社会であっても、
それ以上に仕事を効率化で減らせれば、
実質賃金がプラスになるかもしれません。
第8話:「子どもの絶望」に見えた希望-”大人”の常識はこれからも通用するか?
第8話で参考になると思った箇所、
コチラです。
・歴史を変える非常識な挑戦
<ポイント>
①常識を変えるのは、いつも若者だ
②若者は既得権益や人間のしがらみがちいさいので、古い常識を疑い、迷いなく手放せる
③何かが本当に動き始めるのは、彼らを見守る人たちの心の中にも、変化が起きた時だ
①②のような若者は昔からいるけど、
「出る杭は打たれる」のが日本。
良くも悪くも和を重視しすぎ。
それでは歴史は変えられない、
若者ではない大人がやるべきなのは
③見守って邪魔しないこと。
歳を取ると保守的になるけど、
若者の挑戦を止めるのはやめた方がいい。
歳を取った大人にはできないのだから。
ありがたいと思わないと。
まとめ
各話で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1話:その不安は誰かのビジネス-焦りを生む空気からどう抜け出すのか?
・カネも不安も売る時代
<ポイント>
①2019年、「老後資金が2000万円不足する」という金融庁のレポートが話題になった
②老後の不安なら、地域や家族との支え合いという方法もあるし、定年後も働けるスキルを身につける選択肢だってある
③不安を感じる私たちに金融機関が忍び寄る

第2話:投資とギャンブルの境界線-成功者を真似てもなぜうまくいかないのか?
・健全な投資とギャンブルの見分け方
<ポイント>
①投資の健全性を見極めるシンプルな質問「その利益は、誰の役に立った報酬なのか?」
②値上がり益ばかりを強調する投資は、「自分より高く買ってくれる誰か」が現れなければ成立しない
③他人の財布を狙うということは、あなたの財布も誰かに狙われているということだ
<①誰かの役に立った報酬+他の投資家をあてにしたお金>
・株式投資:①配当+②売却益(or売却損)
・不動産投資:①家賃+②売却益(or売却損)
・預金:①利息のみ
第3話:「会社に守られる」という幻想-労働と投資、報われるのはどちらか?
・「稼ぐ力」の磨き方-仕事から「為事」へ
<ポイント>
・本来、働くこととは、誰かに仕えることではなく、自分の力で価値を生み出すことだ
・長らく社会では、「役に立つこと」と「稼ぐこと」が分断されていた
・人手不足や安泰神話の崩壊を背景に、「役に立つこと」をすれば「稼ぐこと」につながる社会に戻りつつある
第4話:愛と仲間とお金の勢力図-お金以外の何を頼ればいいか?-お金以外の何に頼ればいいか?
・「不安」と「ゴール」の共有戦略
<ポイント>
①「お金の不安」は個人的すぎて共有しにくい
②自分の問題が解決しても、周囲には妬みや距離感が生まれることがある
③学生時代、「社会のために働く」という言葉を「きれいごとだ」と思っていたが、今ではそれが孤立を防ぎ、仲間とつながるための戦略でもあったとわかる
第5話:「あなたのせい」にされた人口問題-なぜ「稼ぐ人が偉い」と思われるのか?
・値上げされた100円は、どこへ消えた?
<ポイント>
・2022年以降、電気代や建築費やうどんのねだんまでが上昇したが、給料はなかなか追いついてこない
・うどんの値上げ分の100円は国内ではなく、海外の生産者の収入となっている
・値上げされた100円は必ず誰かの収入になるが、問題はそのお金が海外に流出していく構造にある
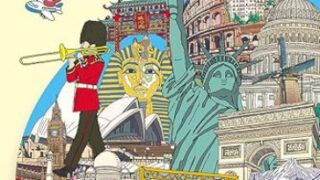
第6話:「お金さえあれば」の終焉-いつまでお金に支配されるのか?
・経済を回せない巨大ピラミッドの罠
<ポイント>
①重要なのは「何に使うか」ではなく、「どれだけ使うか」。経済効果やGDPという数字が、その考えを裏付ける指標としてもてはやされた
②しかし、この考えの前提にあるのは、ヒトもモノも豊富に存在していることだ
③「お金さえ回せば経済はよくなる」という常識は、ヒトもモノも無限に存在するという前提に立った、旧世界の幻想にすぎない
第7話:「仕事を奪う」が投資の出発点-どうすれば仕事を減らせるのか?
・「シイタケ」で読み解く給料アップの秘密
<ポイント>
①長い目で見ると私たちの生活は確実に豊かになった
②1920年から2020年の100年間で、食費は2280倍に上昇したが、給料は5000倍に増えた
③今スーパーで1パック400円のシイタケの値段は、100年前の感覚なら5000円もする高級品だ
第8話:「子どもの絶望」に見えた希望-”大人”の常識はこれからも通用するか?
・歴史を変える非常識な挑戦
<ポイント>
①常識を変えるのは、いつも若者だ
②若者は既得権益や人間のしがらみがちいさいので、古い常識を疑い、迷いなく手放せる
③何かが本当に動き始めるのは、彼らを見守る人たちの心の中にも、変化が起きた時だ
まとめ
お金の不安、
簡単には消えないですよね。
老後2000万円問題を見れば、
仕方ない面もあります。
投資で備えるのは悪くないけど、
ギャンブルに近い投資は避けたい。

ちなみに、
投資以外で備える方法もあります。
人口減で人手不足が進むので、
企業のサービスが行き届かなくなる。
企業の代わりにサービスを提供できれば、
そのまま稼ぐことに直結する。

お金の不安が消えれば安心かというと、
そうでもないです。
お金があっても孤立してしまえば、
精神的にも健康的にも不安は燻る。
人間関係のつながりを残しておくと、
心身ともに豊かな生活を送れます。

現在の日本は、
実質賃金の低下で苦しんでいます。
お金を回せば経済が良くなる、
という旧来の常識はすでに崩壊している。
人口増→人口減に対応できるよう、
社会全体の構造を変える必要がある。
その鍵を握るのは、
少人数でも仕事を回せる効率化ですね。

過去も効率化で生産性が上がり、
私たちの生活は豊かになりました。
効率化のアイデアは若者が持ってるので、
私たちは邪魔せず見守るのみ。
若者の邪魔さえしなければ、
明るい未来は待っているのです。
お金の不安に押しつぶされそうになり、
なんとなく辛い気分でいらっしゃる方は、
いますぐ本書をご覧ください。
本書のお値段は1,650円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
・お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)