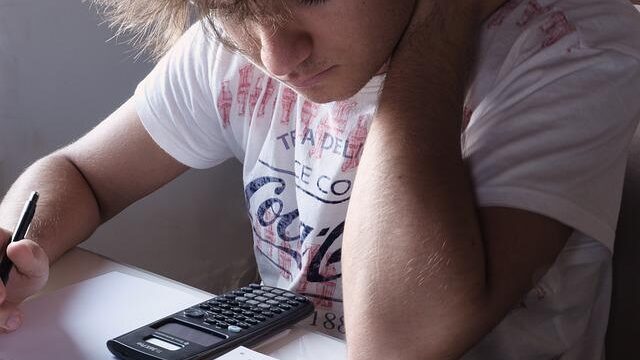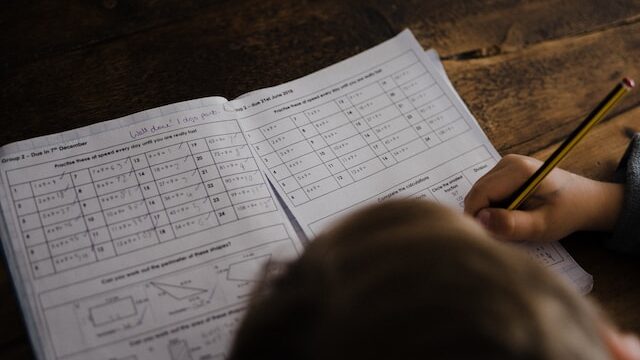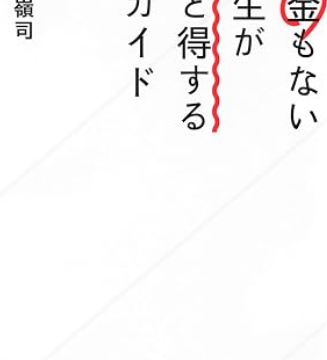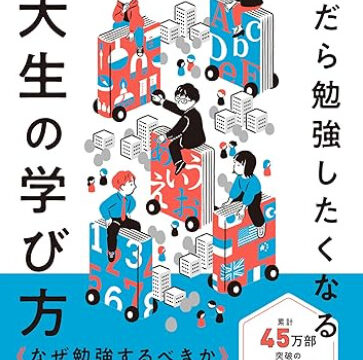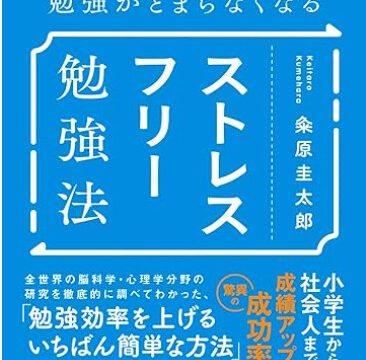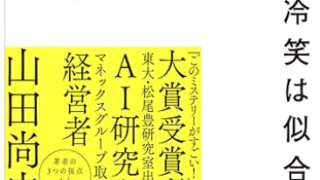【「頑張れない」子をどう導くか ――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感】感想・レビュー
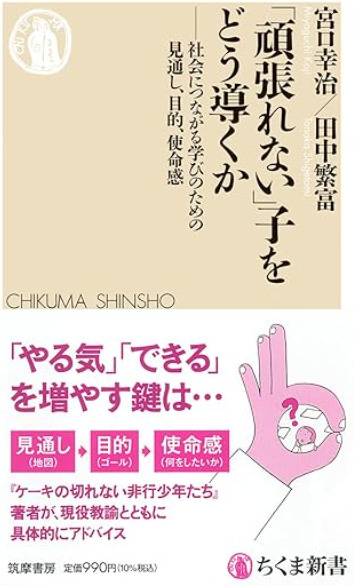
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
『「頑張れない」子をどう導くか ――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感』
子どもがなかなか宿題に取り掛からず、
イライラする時があります。
「先に宿題やって終わらせれば、
後は好きなことやっていいよ」
と言っても順序が逆になる。
先に漫画を読んだり動画を見たりして、
その後に宿題をやる。

ここでいう宿題とはSAPIXです。
SAPIXの宿題量はとにかく多い。
平日はSAPIXや習い事に行くので、
あまり時間はない。
帰宅後に宿題をやる時、
なぜか先に漫画や動画になる。
やっとスイッチが入って宿題するけど、
「眠くて頭が回らない」と言い出す。。

宿題が終わらず翌日に持ち越しが続き、
週末で一気にやることもあります。
でも週末に外出予定があると、
宿題する時間が取れないと言い出す。。
スイッチが入るのが遅すぎる。
計画的に勉強せず中学受験に挑むなんて、
無謀ですよね。
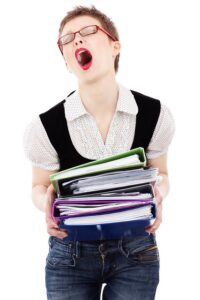
では、
どうすればいいでしょうか?
子どもが勉強するように、
どうにか仕向ければいい。
でも、
どうすればいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
『「頑張れない」子をどう導くか ――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感』
家庭学習ができない子どもに、
どう接すればよいのか?
本書を読んで興味深かったのは、
余計な一言を言わないことですね。
「宿題やったの?」
まさに余計な一言だそうです。

では、
どう言えば子どもは宿題をやるのか?
本書に書かれていますので、
宿題でお悩みの方はぜひご覧ください。
それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:子どもが”見通し”をもてるように
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「宿題したの?」-やる前に言ってしまう
<ポイント>
①このような声かけは、いっそう子どものやる気を削いでしまう
②常にそう言い続けることで子どもが自らやるチャンスや見通しを奪っていることもあるので要注意
③「宿題でわからないことがあったら見てあげるよ」と伝えるくらいにして、子どもが自主的に行動するための手助けをしてあげるつもりでいるのがよい
親なら一度は口にするセリフですね。
言いたくないけど、
言わないと宿題しないので。
宿題をやらないまま学校や塾に行けば、
先生から注意されますよね。
これが続けば親にも連絡が来るし、
本当に悩ましい問題です。

でも、
①②の可能性を考えると、
親は逆に言えなくなってしまう。
①②で本当に良いのか?
親としては不安ですよね。
そこで、
③のように言うと良いそうです。

私は③を言う時があるけど、
本書とは少し場面が違いますね。
どんな場面か?
子どものペンが止まった時です。
たとえば、
問題が解けなくて悩むケースですね。
わからなすぎると勉強が嫌になり、
せっかくのやる気が削がれてしまう。
「わからない箇所は飛ばせ」の意味で、
③を言いますね。
後で教える方が子どもにとっても効率的。
ぜひ実践してみてください。
第2章:子どもの”目的”を支えるために
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・子どもを評価していないか
<ポイント>
・偶然良い点が取れただけだったとしたら、次回も同じように期待されることが、大きな負担になる可能性がある
・テストでいい点数を取ることももちろん大切ですが、子どもにとってもっと大切なのは安心して学べる環境があること
・子どもが求めているのは親からの評価以上に、一緒に喜んでくれたり悔しがってくれたりすること
評価はどうしても切り離せないかな、
と私は思いますね。
テストを受ければ点数は出るし、
通知表で成績評価も出るし。
SAPIXのテストなら順位も出るし、
偏差値も出るし。
親は気になりますよね。

私が重視しているのは、
子どもの成長度合いですね。
過去の自分に比べて成長したか?
いわゆる水平比較です。
他人と比べる水平比較は、
正直あまり意味がない。
偏差値での評価が最たる例。
周り次第でいくらでも変動する。
<垂直に比べる>
・自分の過去と現在を比べること
<水平に比べる>
・自分と他人を比べること
コチラの本に書かれていますので、
ご興味あればぜひご覧ください。
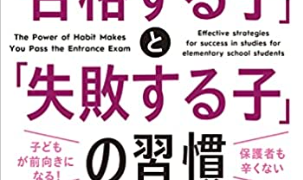
私はSAPIXのテストを振り返る時、
大きく2つのポイントで見ます。
①現時点の学力で解ける問題か?
②現時点の学力で解けない問題か?
①解けるハズなのに間違えた場合、
実にもったいないですね。
たとえば計算ミス。
でも次回克服していれば立派な成長。
間違えた時は悔しいけど、
克服した時は嬉しくなりますね。

②解けない問題は不正解でも仕方ない。
これから覚えればいい。
このように子どもの成長度合いに対して、
適切に評価するなら良いのでは?
あくまで個人的な意見ですが、
皆さんはどう思いますか?
第3章:やる気を”使命感”に繋げるために
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・学歴のため?稼ぐ力のため?
<ポイント>
①子どもたちが勉強したからといって、皆が高い学歴を手に入れられるとは限らない
②国内において全国的に有名な一部の大学を除けば、わずかな偏差値の違いが人生を大きく左右するとは考えにくい
③社会人になって初めて、学歴が実社会で持つ意味の限界を、身を持って体験する
②を知っていれば、
①で絶望することないです。
少なくとも大卒であれば、
高卒より生涯収入は高いです。
実は一番厳しい現実、
③かもしれません。
高学歴で大企業に入社できても、
リストラにあう可能性があるのです。

では、
何のために勉強するのか?
私は子どもにこう話します。
大卒で就職&生涯収入を稼ぐ目的で、
選択肢を持つために勉強する。
学力がないことには大学に入れず、
大卒の生涯収入も期待できない。
大卒→就職の選択肢を持ちつつ、
最後は自分で決めればいい。
大卒以外でも稼ぐ道はあるけど、
再現性がなく難しいのが現実。

こんな感じで、
わりと現実的な話をしますね。
勉強しなければ、
稼ぎが少ない未来になる確率が高い。
今の生活レベルは維持できず、
本人がどう感じるかはわからない。
どうするかは子ども次第だけど、
勉強した方が将来の選択肢は広がる。
将来のことは大学入ってから考える。
それでよいと思ってます。
就職後のことは自分で考えましょう。
もう自立した大人なのですから。
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:子どもが”見通し”をもてるように
・「宿題したの?」-やる前に言ってしまう
<ポイント>
①このような声かけは、いっそう子どものやる気を削いでしまう
②常にそう言い続けることで子どもが自らやるチャンスや見通しを奪っていることもあるので要注意
③「宿題でわからないことがあったら見てあげるよ」と伝えるくらいにして、子どもが自主的に行動するための手助けをしてあげるつもりでいるのがよい
第2章:子どもの”目的”を支えるために
・子どもを評価していないか
<ポイント>
・偶然良い点が取れただけだったとしたら、次回も同じように期待されることが、大きな負担になる可能性がある
・テストでいい点数を取ることももちろん大切ですが、子どもにとってもっと大切なのは安心して学べる環境があること
・子どもが求めているのは親からの評価以上に、一緒に喜んでくれたり悔しがってくれたりすること
<垂直に比べる>
・自分の過去と現在を比べること
<水平に比べる>
・自分と他人を比べること
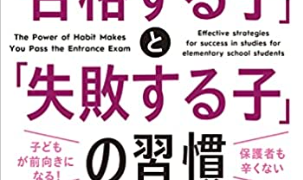
第3章:やる気を”使命感”に繋げるために
・学歴のため?稼ぐ力のため?
<ポイント>
①子どもたちが勉強したからといって、皆が高い学歴を手に入れられるとは限らない
②国内において全国的に有名な一部の大学を除けば、わずかな偏差値の違いが人生を大きく左右するとは考えにくい
③社会人になって初めて、学歴が実社会で持つ意味の限界を、身を持って体験する
まとめ
子どもが勉強しない時、
親は本当に悩みますよね。
宿題ができなければ、
家庭学習の習慣が身につかない。
将来の受験勉強を見据えると、
本当に大丈夫だろうか?
でも声がけすれば、
逆に子どもはやる気が削がれる。

「わからないことがあれば聞いてね」
という声がけはいいけど1つご注意。
親が必ず答える前提でないとダメ。
わからなければ調べてでも答える。
これくらいの気概がないと、
子どもに見透かされる。
私はSAPIXの宿題の丸つけや、
間違えたりわからない問題を解きます。
量も多く難しくて結構大変だけど、
これくらい本気の姿勢を見せないと。

子どもの成績については、
冷静な見方が必要ですね。
他人と比べるのではなく、
過去の自分と比べる。
子どもの成長度合いに応じて、
学力が伸びているかを評価する。
点数や偏差値に一喜一憂ではなく、
きちんと中身を評価しましょう。

何のために勉強するか?
意見がわかれる箇所ですね。
個人的には、
大卒で就職&生涯収入を稼ぐ目的で、
選択肢を得るためと考えます。
高卒より大卒の方が、
生涯年収が高いのは事実。
高卒で上回ることもできるけど、
再現性に乏しい。
将来どう稼ぐかは今決める必要ない。
大学で決めるために勉強すればいい。
あくまで個人的な見解だけど、
現実に即した考え方ですね。

子どもが勉強しないとお悩みの方、
いますぐ本書をお買い求めください。
子どもはなぜ勉強しないのか?
親はどうすればいいのか?
親の声がけ一つで、
子どもの勉強は変わります。

親が言ってはいけない言葉は何か?
親が言ってあげるべき言葉は何か?
本書を読んで実践すれば、
きっと子どもは家庭で勉強しますね。
それが受験勉強につながり、
入試で合格へと導くでしょう。
もし大卒なら生涯年収は高くなり、
子どもの将来にもプラスですよね。
子どもの将来のために、
ぜひ本書をお買い求めください。
本書のお値段は990円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
・「頑張れない」子をどう導くか ――社会につながる学びのための見通し、目的、使命感
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)