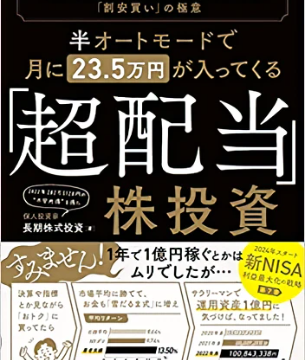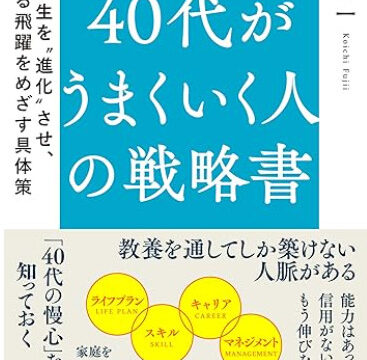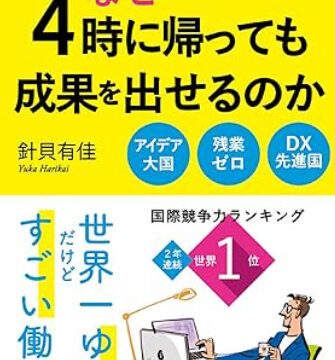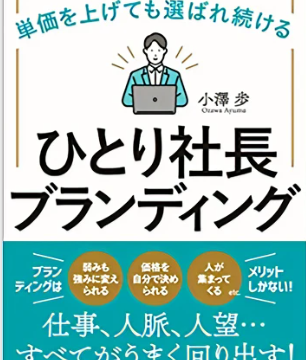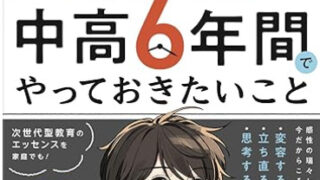【日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?】感想・レビュー
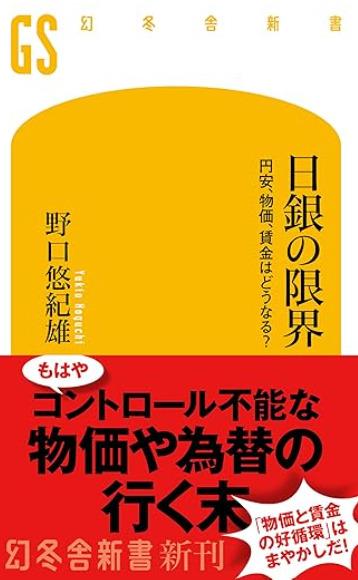
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
あなたの生活、
豊かになってますか?
給料が増えない。
物価高で生活費が苦しい。
貯金なんて全然できない。
豊かな生活とは、
全然かけ離れてますよね。

でも最近、
給料が上がり始めています。
新卒の給料はもちろん、
春闘で5%アップの会社もチラホラ。
日本経済は失われた30年から脱し、
経済成長が見込める状態になった。
…と思っている方、
この先も豊かになれないです。

なぜ豊かになれないのか?
給料の伸び以上に、
物価が伸びているからです。
物価高は止まる気配がなく、
何もしなければお金は減るばかり。
これでは困りますよね。

では、
どうすればいいでしょうか?
日本の現実から将来を予測し、
お金の対策を考えればいい。
でも、
どのようにすればいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
円安/物価/賃金がどうなるか?
本書を読むとよくわかります。
残念ながら、
悲観的にならざるを得ません。
でもこれが現実。
それを受け止め対策を立てればいい。
現実逃避してもお金は増えない。
本書で現実と見通しを学びましょう。
そして、
対策の部分はあまり書かれてないので、
私が後ほど補足しますね。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログでご紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:「異常な円安」に依存した株価が大暴落
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第1章のまとめ
<ポイント>
・2024年8月初めに、日経平均株価は歴史的な大暴落を記録した
・2022年以降のアメリアの利上げに伴世界各国の中央銀行が追随したが、日銀だけが低金利を継続した。円の独歩安が進み、日本企業の利益が増大して、株価が上昇した
・アメリカの金利引き下げで状況が変わり、日本の株価が暴落した
世界の中銀と日銀の動き、
真逆なのが注目ポイントです。
簡単にまとめたのがコチラ(↓)
<2022年>
・ウクライナ戦争後に、世界中で物価高が発生
・物価高を抑えるために、世界中で利上げを実施
・日本は金融緩和維持のため、利上げせず
<2024年>
・世界中で物価高に陰りが見えてきた
・世界中で利下げを実施
・日本は金融緩和を止めたため、利上げ実施
もし2024年に利上げしなければ、
日経平均の暴落はなかったですね。
それでも2025/2/18現在、
39000円台をキープしてます。
ドル円151円台と異常な円安は変わらず、
輸出企業の株価を支えている。

2022年のドル円115円台に戻るのは、
想像しにくい。
異常な円安は今後も続くけど、
その恩恵で日経平均は株高維持と予想。
つまり、
投資した方がお得ってことですね。
第2章:円安がもたらした弊害と混乱
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第2章のまとめ
<ポイント>
・円安のためにマナーの悪い外国人が増え、観光郊外が地域住民の生活に無視できぬ影響を与えている
・日本から海外の留学生数は、2004年頃から傾向的に減少している
・新NISAと円安によって、資金の海外流出が増えている
円安なのでインバウンドで稼ぐのは、
合理的だと思う。
でも質の悪い外国人観光客が増え、
観光地で被害が出ているのも事実。
個人的には、
二重価格を導入する時期だと思ってます。
外国人には高価格とし、
払えないなら日本に来なくてもいい。
払える質の高い外国人だけになるのが、
理想的な解決策ですよね。

海外留学は今後も増えないでしょうね。
円安の問題もあるけど、
実質賃金が増えないのも問題です。
賃上げのニュースが飛び交うけど、
それ以上に物価高が進んでます。
相殺すると給与が減っているようでは、
留学費用を出せないですよね。

新NISAで海外投資するのは、
理にかなってますね。
日本株より外国株の方が、
利益が見込めるから。
日本経済にマイナスの意見もあるけど、
個人的にはそう思わないですね。
外国投資で資産を増やし、
日本で消費すれば良いと思うので。
日本で稼げない以上、
海外投資で稼ぐのは合理的ですね。
コチラの本が参考になるので、
ご興味あればぜひご覧ください。

第3章:「円安カジノ経済」の分析
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第3章のまとめ
<ポイント>
・日本経済は利上げに対する耐性を持たないため、金利を十分な高さに引き上げられないという問題がある
・日銀の利上げの理由として、「賃金と物価の好循環が始まっている」ことをあげているが、これが好ましい現象だとの判断は間違っている
・必要なのは、円安の進行を抑え、物価上昇を抑えることだ
ポイント3つ目、
2022年以降の世界の中銀施策ですね。
利上げをするのは、
加熱した景気を冷やすのが普通です。
つまり、
物価高では利上げが正解なのです。

しかし、
日銀は利上げしませんでした。
いや、
ポイント1つ目の通り、
利上げできなかったのが実情かと。
だからいま少しずつ利上げし、
元に戻そうとしている。

でも、
好循環なのにわざわざ利上げして、
景気を冷ますのは本来おかしい。
ポイント2つ目は、
強引でおかしな理屈なのです。
日銀もわかってはいるけど、
金利正常化を最優先にしているのかと。
円安と物価高が止まらない利上げ、
今後どうなるか要注目ですね。
第4章:日銀は円安を放置するが、株価下落には敏感
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第4章のまとめ
<ポイント>
・株価が下落すれば、日銀は利上げしないのか?
株価が下落すれば、
日銀は利上げしにくいでしょうね。
利上げで株価暴落が起きると、
○○ショックと呼ばれるから。
○○に入るのは日銀総裁の名前、
直近だと2024年8月の植田ショック。
政府からも批判されるし、
できれば避けたいですよね。
今後もこの傾向は変わらないですね。
第5章:正常な世界に戻れば、どこまで円高になる?
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第5章のまとめ
<ポイント>
・2023年の円の購買力平価は、1ドル90~95円程度だ
<購買力平価とは>
・モノやサービスの値段を基準にした為替レート
・モノやサービスの価格は世界どこでも一物一価に基づく計算
2025/2/18現在、
ドル円は150円台です。
購買力平価と比べると、
かなり乖離がありますよね。
でも購買力平価のような円高が、
再び来るのは想像しにくいですね。

たとえば2011年の東日本大震災後、
ドル円75円台になったことあります。
しかし円高で国内企業が悲鳴を上げ、
経済はまったく成長しませんでした。
2012年に政権交代以降は、
金融緩和で円安基調になりました。
そこから景気が少しずつ回復したので、
購買力平価の円高には誘導しないかと。
円高進行したとしても、
2022年以前の115円前後が現実的かも。
第6章:インフレに便乗し利益を増やす「強欲資本主義Ⅰ」
第6章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第6章のまとめ
<ポイント>
・大企業では粗利益が増加して、経常利益が著しく増加した。これは円安による輸入物価の上昇分を販売価格に転嫁したからだ
・賃金が上昇しているのは大企業のことであり、中小零細企業では賃金は停滞している
・中小零細企業は賃上げ分を取引の次段階に転嫁できないからだ
2022年からの物価高で儲けたのは、
大企業のみです。
大企業は価格転嫁できるけど、
中小企業は価格転嫁できないから。
もし中小企業が価格転嫁すれば、
次の取引を簡単に失うリスクがある。
いくら政府が価格転嫁を促しても、
中小企業にはできないのです。

春闘で5%以上の賃上げができるのも、
大企業に限られますね。
中小企業には難しい話だし、
大企業に批判が集まるのもわかる。
でも中小企業がいつの時代でも、
5%以上の賃上げは難しいとも思う。

高収入を目指すなら、
新卒で大企業に入るのがベストです。
大企業の社員も全員が優秀ではない。
要はそこに在籍しているかどうかだけ。
コチラの本に書かれていますので、
ご興味あればぜひご覧ください。
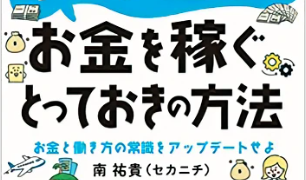
第7章:輸入物価の下落を還元しない「強欲資本主義II」
第7章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第7章のまとめ
<ポイント>
①輸入物価が上昇した時には、企業は販売価格を引き上げ、消費者など最終財の購入者に負担を転嫁してきた
②2023年に輸入物価が下落した時には、これを消費者物価に還元しなかった
③大企業の利益が増加したが、賃金を引き上げなかったので、経常利益が著しく増大した
①世の中が値上げモードになったのは、
企業にとって絶好の機会でした。
それまでずっとデフレが続き、
値上げしたくてもできなかったから。
輸入物価の上昇が大義名分となり、
ここぞとばかりに値上げラッシュ。

問題なのは②です。
輸入物価が下がっても、
値下げはしませんでした。
わざわざ利益を減らしたくないから。
一度値上げしたら簡単に下げない。
しかも当初は賃上げも渋く、
企業業績だけが伸びる結果に。
官製春闘しないと賃上げしない国。
それが日本の現状なのです。
第8章:価格転嫁で賃上げを実現する「強欲資本主義III」
第8章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第8章のまとめ
<ポイント>
①2023年春闘から賃金上昇が目立つようになった
②本来、賃上げは生産性向上によって実現すべきものだが、日本では販売価格に転嫁されて消費者が負担する「悪い賃上げ」が始まろうとしている
③実質賃金下落は長期的現象だ
官製春闘で賃上げが目立つけど、
決して喜べる状況ではないです。
賃上げより物価高の方が伸びていて、
実質賃金は下がっているので。
物価高対策のために、
企業が無理やり賃上げしてるのが実態。
物価高以上の賃上げをしてるのは、
一部の大手企業のみです。
大多数は実質賃金が低下し、
豊かになっていないのが問題なのです。
第9章:円安に頼らぬ長期成長は実現できるのか?
第9章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第9章のまとめ
<ポイント>
・AIはこれからの世界の基本方向を決める、極めて重要な技術だ
・AIは長期戦略の核にすべきものであるのに、政治の場では、あまり関心がもたれていない
AIのようなデジタル戦略、
今後は必須ですね。
日本は人口減になるので、
労働減にもなります。
そこでAIを活用し、
生産性向上しないと経済成長しない。

しかし、
政治の場ではAI規制がメインに。
これでは経済が伸びないですよね。
世の中の経済成長に期待できないなら、
AI投資で個人資産を増やすしかない。
AI技術の最先端は米国なので、
米国投資がオススメですね。

第10章:日米新政権で、日本経済はどうなる?
第10章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・第10章のまとめ
<ポイント>
・トランプ氏の経済政策は、企業よりのものと考えられる
・高関税の賦課は、日本の自動車メーカーにも大きな影響を与える
・長期的に見れば、アメリカの成長をも阻害することになる
自動車関税25%、
まさにいま話題になってます。
もし4月から適用されれば、
日本経済への影響は大きい。
自動車メーカーの下には、
数多くの下請け企業がいます。
一気に売り上げが落ち込めば、
一時的には苦しくなるでしょう。

でも、
長くは続かないと思ってます。
25%関税で車の価格は上がり、
米国民が車を買いにくくなるから。
米国経済の減速要因にもなり、
どこかで限界が来るでしょう。
それまで耐えられるかが、
勝負の分かれ目ですね。
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
コチラです。
第1章:「異常な円安」に依存した株価が大暴落
・第1章のまとめ
<ポイント>
・2024年8月初めに、日経平均株価は歴史的な大暴落を記録した
・2022年以降のアメリアの利上げに伴世界各国の中央銀行が追随したが、日銀だけが低金利を継続した。円の独歩安が進み、日本企業の利益が増大して、株価が上昇した
・アメリカの金利引き下げで状況が変わり、日本の株価が暴落した
<2022年>
・ウクライナ戦争後に、世界中で物価高が発生
・物価高を抑えるために、世界中で利上げを実施
・日本は金融緩和維持のため、利上げせず
<2024年>
・世界中で物価高に陰りが見えてきた
・世界中で利下げを実施
・日本は金融緩和を止めたため、利上げ実施
第2章:円安がもたらした弊害と混乱
・第2章のまとめ
<ポイント>
・円安のためにマナーの悪い外国人が増え、観光郊外が地域住民の生活に無視できぬ影響を与えている
・日本から海外の留学生数は、2004年頃から傾向的に減少している
・新NISAと円安によって、資金の海外流出が増えている

第3章:「円安カジノ経済」の分析
・第3章のまとめ
<ポイント>
・日本経済は利上げに対する耐性を持たないため、金利を十分な高さに引き上げられないという問題がある
・日銀の利上げの理由として、「賃金と物価の好循環が始まっている」ことをあげているが、これが好ましい現象だとの判断は間違っている
・必要なのは、円安の進行を抑え、物価上昇を抑えることだ
第4章:日銀は円安を放置するが、株価下落には敏感
・第4章のまとめ
<ポイント>
・株価が下落すれば、日銀は利上げしないのか?
第5章:正常な世界に戻れば、どこまで円高になる?
・第5章のまとめ
<ポイント>
・2023年の円の購買力平価は、1ドル90~95円程度だ
<購買力平価とは>
・モノやサービスの値段を基準にした為替レート
・モノやサービスの価格は世界どこでも一物一価に基づく計算
第6章:インフレに便乗し利益を増やす「強欲資本主義Ⅰ」
・第6章のまとめ
<ポイント>
・大企業では粗利益が増加して、経常利益が著しく増加した。これは円安による輸入物価の上昇分を販売価格に転嫁したからだ
・賃金が上昇しているのは大企業のことであり、中小零細企業では賃金は停滞している
・中小零細企業は賃上げ分を取引の次段階に転嫁できないからだ
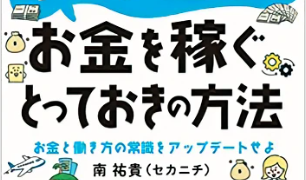
第7章:輸入物価の下落を還元しない「強欲資本主義II」
・第7章のまとめ
<ポイント>
①輸入物価が上昇した時には、企業は販売価格を引き上げ、消費者など最終財の購入者に負担を転嫁してきた
②2023年に輸入物価が下落した時には、これを消費者物価に還元しなかった
③大企業の利益が増加したが、賃金を引き上げなかったので、経常利益が著しく増大した
第8章:価格転嫁で賃上げを実現する「強欲資本主義III」
・第8章のまとめ
<ポイント>
①2023年春闘から賃金上昇が目立つようになった
②本来、賃上げは生産性向上によって実現すべきものだが、日本では販売価格に転嫁されて消費者が負担する「悪い賃上げ」が始まろうとしている
③実質賃金下落は長期的現象だ
第9章:円安に頼らぬ長期成長は実現できるのか?
・第9章のまとめ
<ポイント>
・AIはこれからの世界の基本方向を決める、極めて重要な技術だ
・AIは長期戦略の核にすべきものであるのに、政治の場では、あまり関心がもたれていない

第10章:日米新政権で、日本経済はどうなる?
・第10章のまとめ
<ポイント>
・トランプ氏の経済政策は、企業よりのものと考えられる
・高関税の賦課は、日本の自動車メーカーにも大きな影響を与える
・長期的に見れば、アメリカの成長をも阻害することになる
まとめ
日銀が利上げしても、
円安は今後も続くでしょうね。
米国が物価高再燃で、
利下げが止まりつつあるので。
関税政策で物価高が厳しくなれば、
米国は再び利上げでもおかしくない。
日本と米国のどちらが経済成長するか?
米国の方が可能性高いですよね。
だからマネーは米国に流れ、
日本の円安は今後も続くと予想します。

物価高はどうなるか?
これも止まらないでしょうね。
デフレの期間、
企業はずっと値上げできなかったから。
念願の値上げで利益増したのに、
再度値下げで利益減には戻さない。
企業が相当ピンチにならない限り、
物価高は残念ながら続きます。

名目賃金は上がると思うけど、
実質賃金は下がるでしょうね。
物価高の勢いが強すぎて、
これを上回る賃上げが難しいから。
これをできるのは一部の大企業のみ、
圧倒的多数は実質賃金減となる。

円安止まらず。
物価高止まらず。
実質賃金減止まらず。
日本の将来は、
残念ながら厳しいのが現実です。
このような見通しを知らないと、
貯金で備えようとする。
貯金金利では物価高を超えられず、
実質目減りすることも知らない。
これでは困りますよね。

日本の現実を知り、
いまから将来に備えたい方。
いますぐ本書をお買い求めください。
日本で稼いで将来に備えるのは、
難しいことに気づくでしょう。
それならば海外投資して、
資産を増やせばいいことに気づくハズ。
自分の身は自分で守る。
いまからから将来に備えましょう。
本書のお値段は1,122円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
ちなみに海外投資なら、
米国株がオススメです。
米国は経済成長が見込めるし、
簡単に投資できますし。
コチラの本がわかりやすいので、
併せてお買い求めください。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学4年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)