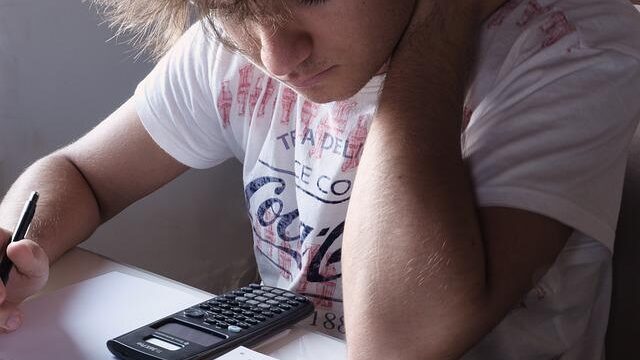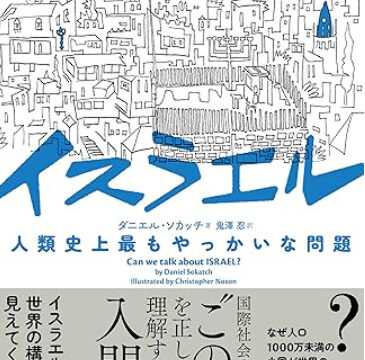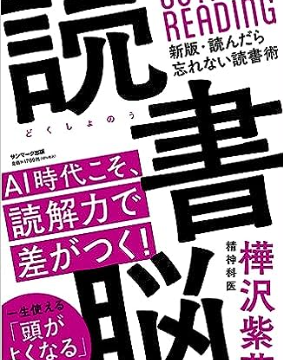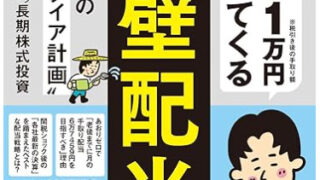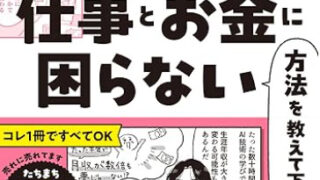【第2回志望校診断サピックスオープン(5年)②】時間配分を変えただけで偏差値70超え!サピックスオープンの傾向と対策とは?
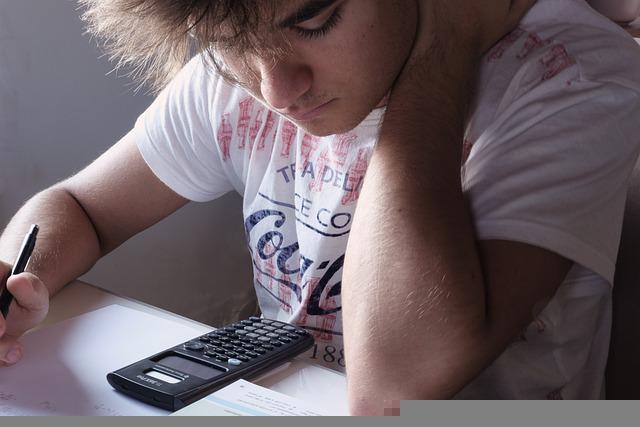
はじめまして、はるパパです。
さて、
8/31のテスト結果が発表されました。
前回の結果については、
↓のブログをご覧ください。

前回達成できなかった成績上位5%、
見事に達成しました。
それどころか上位1%以内になり、
偏差値70を超えました。
理解以外の3科目で、
大幅に成績アップしたのが大きい。
前回の反省を踏まえ、
傾向と対策が功を奏しましたね。
↓にも書いたけど、
時間配分を事前に考えてヨカッタ。

今回は時間配分を中心に、
4科目の結果を振り返ってみます。
皆様の参考になれば幸いです。
国語
国語のテスト、
以下の3分野から出題でした。
前回より偏差値が10以上アップ!
時間配分が大成功!
前回は全部終わらなかったけど、
今回は全部終わった。
どのようにうまくいったのか?
後ほど解説します。
1.漢字の読み書き
2.物語文の読解
3.説明文の読解
↓のブログでも少し触れましたが、
前回より大問が1つ減ってます。
でも時間ギリギリで終わった感じ。
その理由は明白で、
2の問題文がとにかく長い。
逆に3はすごく少ないので、
1→2→3の順にやると失敗する。

前回の傾向を踏まえて、
1→3→2で解いたのは正解でした。
子どもは3.説明文の方が得意なので、
とにかく早く終わらせる。
そして長文の2.物語文に取り組み、
記述問題を全部終わらせる。
記述問題は配点が高いので、
ゼロ回答だと大幅な減点になります。
偏差値が10以上アップしたのは、
間違いなく時間配分のおかげ。

課題を挙げるとすれば、
記述解答の精度を上げることですね。
時間に追われているので、
すべて満点の回答を書くのは難しい。
でも、
配点の半分以上は取ってほしい。
ほぼ満点の記述もあれば、
ほぼゼロ点に近い記述もあった。
スピードと精度の両立、
Bテキストの宿題で実践してみます。
算数
算数のテスト、
以下の7分野から出題でした。
前回より偏差値が8アップだけど、
成績が劇的に上がったわけじゃない。
偏差値アップの要因は、
前回より平均が下がったけど、
自分の成績は上がったからですね。
算数も時間配分が功を奏したかも。
後ほど詳しく解説します。
1.計算問題
2.小問集合
3.図形問題
4.速さ
5.規則性
6.場合の数
7.立体図形(展開図)
前回より平均が下がったのは、
大問の数の影響ですね。
前回は大問6つだったけど、
今回は7つです。
制限時間は変わらないので、
前回よりもさらに厳しかったハズ。

前回は最後まで辿り着けなかったので、
まともにやったら今回も終わらない。
でも↓に書いた通り、
時間配分を事前に考えて臨んだ結果、
最後の問題まで辿り着くことはできた。
後半は難問が多いので、
解ける問題を優先的に1問でも多く解く。
今回点数が伸びた要因は、
後半で解けた問題の部分でしたね。

課題を挙げるとすれば、
Bの思考力問題ですね。
特に6,場合の数、
本人が苦手にしてる単元です。
自分でもマズイと思ったらしく、
先日の小テスト前も勉強してました。
基礎ができないと、
応用力が問われる思考力問題は解けない。
まだ小5なので基礎固めを重視し、
思考力問題は徐々に慣れる感じかな。
理科
理科のテスト、
以下の4分野から出題でした。
成績は前回と変わらず好成績。
大問が前回より1つ多くキツかったけど、
最後まで全部辿り着けたのは良かった。
ただし課題も見えました。
後ほど詳しく解説します。
1.小問集合
2.水溶液の性質
3.物体の運動
4.植物
課題は何か?
また資料問題で得点を落としたこと。
資料見ればわかるのになぜ?
と思うけど時間がかかるらしい。
計算を伴う問題が多く、
そこに時間を取られるらしい。

ということは、
資料問題を後回しの方が良いのかも。
簡単なA問題をいかに素早く解いて、
B問題の時間を確保できるか?
時間配分は算数に近いのかもしれない。
次回に向けて子どもと話してみます。
社会
社会のテスト、
前回同様に1分野のみの出題でした。
先日の夏期講習マンスリーで油断し、
大きく得点を落とした社会。
テキストやアトラスに目を通し、
手を抜かない努力をしてましたね。
その結果、
前回より偏差値が8アップ!
前回より成績が上がった要因は何か?
後ほど詳しく解説します。
・船をテーマにした問題
成績が良かった要因は、
B.記述問題が満点だったことです。
前回の反省点は、
記述で大きく点数を落としたこと。
記述の書き方は国語で学び、
あとは知識をつけるのみ。
朝は必ずニュース見てるし、
自分なりに考えて意見も言う。
わからないことは親に聞いてくるし、
教えればすぐに覚える。
普段から時事問題に興味関心がないと、
記述で得点を重ねるのは難しいですね。
まとめ
今回の成功要因は、
傾向と対策がうまくハマったことですね。
前回のテストで傾向がわかったので、
得点が伸び悩んだ要因の分析。
時間配分に改善の余地があるとわかり、
事前に大問ごとの時間配分を仮決め。
時間配分を守れば最終問題まで辿り着き、
正解数も増えて得点も伸びる。

サピックスオープンのカギを握るのは、
B問題の得点ですね。
ここで大きく点を落とすと、
他でカバーするのが難しくなる。
たとえば、
国語/理科/社会なら記述問題とか、
算数なら後半2つの大問とか。
A問題をいかに素早く解き、
B問題をもれなく全部解けるか?
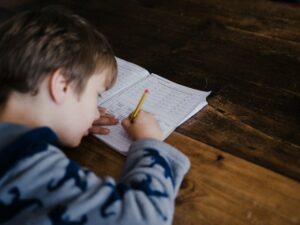
前回は成績上位5%に入れなかったけど、
今回は見事に達成。
それどころか上位1%以内になり、
偏差値70を超えました。
志望校判定はすべて合格率80%となり、
前回終了後に立てた目標を達成。
前回のブログに書いたことが現実に。
さすがに無謀だろうと思ってたけど、
本当に達成するとは思わなかった。。

次回が同じようにうまくいく保証は、
どこにもありません。
あまり根詰めすぎるとパンクするし、
本番はまだ1年以上先です。
受験勉強はマラソンだと思ってるので、
ペース維持が重要。
いかに好成績を維持できるか?
あまり張り切り過ぎてバテないよう、
親が注意して見守ろうかなと思ってます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)