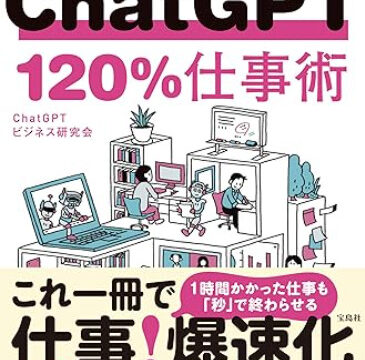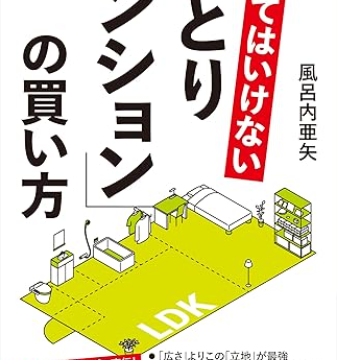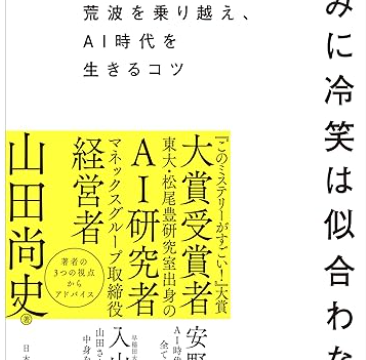【なぜあの人は同じミスを何度もするのか】感想・レビュー
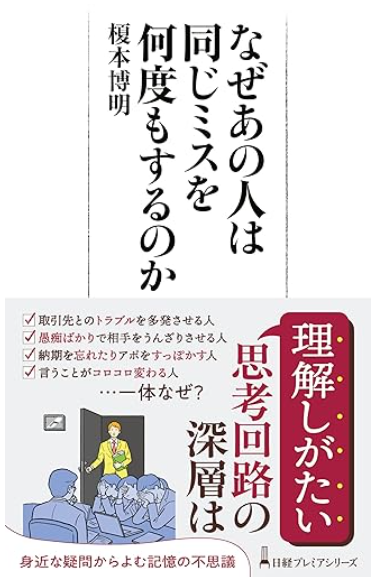
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
なんであの人は何度言っても、
同じミスを繰り返すのだろうか?
職場や家庭で、
そんな疑問を抱いたことありませんか?
「前にも言ったのに」
「なんで覚えてないの?」
「記憶力が悪すぎじゃないの?」

イライラが募り、
対人関係でストレスを抱える。
相手の性格の問題では?
と思いたくなりますよね。
でも実は、
人間の記憶や気分/解釈のクセに、
問題があるのです。

人間の記憶や気分/解釈のクセ?
何それ?って感じですよね。
私もコチラの本を読むまでは、
知りませんでした。
本書では心理学の知見をベースに、
↓のメカニズムを解説しています。
・繰り返される問題行動
・認知のズレ
本書を読むと、
他人の問題行動に寛容になれます。

①「これは悪気ではない」
②「脳のクセなんだ」
③「自分にも起こり得るのか」
③は驚きですが、
記憶違いは誰でも起こるそうです。
これこそがまさに、
人間の記憶や気分/解釈のクセなのです。

では、
問題行動や認知のズレから抜け出すには、
どうすればいいでしょうか?
本書では課題を具体的に示しつつ、
実践的な対処法が提案されています。
これを実践すれば、
対人関係のストレスから解放されますね。
人間関係の悩みのほとんどは、
記憶や感情のズレによるすれ違いです。
そんなすれ違いを乗り越え、
ストレスフリーな人間関係を築きたい。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
第1章:なぜあの人は何度注意しても同じミスをするのか
第1章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・同じミスを繰り返すと人が抱える本質的な問題
<ポイント>
①なぜミスをしたかという視点から自分のやり方を振り返り、まずい点をチェックするということができていない
②記憶がすぐに消えてしまう場合は、認知能力の問題をカバーする工夫が必要となる
③記憶の保持に問題がある場合、紙にメモして机に貼り自然と目につくようにする
同じミスを繰り返す人は、
信頼を失います。
若いうちのミスは許されても、
歳を重ねれば周りの目は厳しくなる。
自分を振り返りできない。
再発防止を考えられない。
もう成長が見込めない。
評価は下がる一方ですよね。

電子化の影響で、
最近は紙でメモ取る人は減りました。
PCにもメモ帳はあるけど、
開くことを忘れたらミスが再発する。
それなら紙にメモを取り、
PCに貼り付けた方がいつでも目に入る。
いつでも目にすれば、
さすがに忘れないですよね。
同じミスを繰り返す人には、
③を促しましょう。
ミスが減れば周りの評価も変わり、
対人関係もスムーズになりますね。
第2章:なぜあの人はいつも愚痴ばかりなのか?
第2章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・愚痴の多い人はほんとうにひどい目に遭っているのか
<ポイント>
①愚痴っぽい人は、けっして嫌な目にばかり遭っているわけではなく、ポジティブな出来事もたくさん経験している
②わざわざネガティブな出来事ばかりを選んで思い出しては嘆いている
③愚痴っぽい人は常にネガティブな気分で過ごしており、自分の気分に馴染むネガティブな出来事ばかりを記憶してしまう
③気分一致効果と言うそうです。
対策は簡単で、
③ポジティブな気分でいればいい。
そのためには、
わざとでも笑顔になると良いらしい。
笑顔がポジティブな気分を生み、
ポジティブな記憶を思い出す。
もし周りで愚痴の多い人がいたら、
ぜひ笑顔を呼びかけてみましょう。
笑顔が多い環境は、
対人関係も良好ですよね。
第3章:なぜあの人は言うことがコロコロ変わるのか
第3章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・人間の記憶は意外とあっさりと書き換えられる
<ポイント>
・言うことがコロコロ変わる人物ばかりでなく、自分自身の記憶もいつの間にか自覚なしに変容している可能性がある
・自分自身で経験したことだと思い込んでいる記憶の中にも、じつは両親をはじめとする身近な人たちの経験を取り込んだもので自分自身では経験していないことがらがけっこう含まれている
・無用なトラブルを防ぐためにも、くれぐれも自分の記憶を絶対視しないよう注意したい
言うことがコロコロ変わる人は、
記憶が書き換えられているとは。。
本書の実験例を読むと、
記憶の書き換えが容易なのが一目瞭然。
言うことがコロコロ変わるって、
他人に対して感じたことはある。
でも同じくらい、
私もそう思われたことはある。
記憶を絶対視せずトラブルを防げば、
対人関係もうまくいきますよね。
第4章:なぜ同じ経験をしているのに記憶がスレ違うのか
第4章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・「言ったつもり」のトラブルはなぜなくならないのか
<ポイント>
①記憶のスレ違いというのがけっして珍しいことではなく、だれもが日常的に悩まされており、気になっている
②「何度も経験している出来事は混同されやすい」という心理的メカニズムが絡んでいる
③普段から似たようなやりとりが多い場合は、別のときの記憶が紛れ込みやすいため、記憶のすれ違いが頻繁に起こりがち
言った言わないのトラブル、
一度は経験ありますよね。
個人的には仕事より、
家族間(特に夫婦間)や多い。
私も妻によく指摘されるけど、
夫婦間の会話は②が要因なのかも。
その際の対応は言い争いせず、
さりげなく話題を変えると良いらしい。
無用なトラブルを避けるのが、
夫婦円満の秘訣ですね。
第5章:なぜ昔の歌は覚えているのに最近の歌は覚えられないのか
第5章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・なぜ10代20代の思い出は特に鮮明なのか
<ポイント>
①40代も70代も、10代~20代のことはよく覚えている
②①の理由はいくつかの説があるが、私は自己のアイデンティティに関連付けて解釈する立場を取っている
③10代~20代の時期の記憶には、いまの自分の成り立ちをうまく説明するエピソードがたくさん詰まっており、そのためによく思い出す
40代になって実感したけど、
最近の歌は覚えられないです。
友人との会話に出てくるわけでもないし、
カラオケで歌うわけでもない。
特に困らないので気にしてないけど。

②③はなるほどなぁ、
と思いましたね。
同年代と飲みに行っても、
昔の話はポンポン出てくる。
カラオケに行っても、
当時の歌はいまでも歌える。
昔の記憶を忘れなければ、
40代の対人関係は問題ないですね。
第6章:なぜあの人と話すと記憶が変わっていくのか
第6章で参考になると思った箇所、
コチラです。
・モチベーションの低い人物への対処法
<ポイント>
①私たちの過去は変えられる
②過去の出来事の意味を変えることは、十分に可能である
③過去の記憶を掘り起こし、何をやってもダメな自分、いくら頑張ってもダメな自分という自伝的記憶の意味づけを変えることで、過去の景色は変わり、モチベーションも上がってくることが期待される
過去の出来事は変えられないが、
その出来事の意味は変えられる。
たとえば、
過去の辛い出来事が、
いまとなっては良い教訓になる。
出来事自体は変わってないけど、
解釈を変えることで意味が変わる。
この考え方ができると、
③モチベーションアップが期待できる。
モチベーションの低い人物がいる場合、
①~③のアプローチをすると良いかも。
その人のモチベーションが上がれば、
対人関係も良くなりますよね。
まとめ
各章で参考になると思った箇所、
まとめました。
第1章:なぜあの人は何度注意しても同じミスをするのか
・同じミスを繰り返すと人が抱える本質的な問題
<ポイント>
①なぜミスをしたかという視点から自分のやり方を振り返り、まずい点をチェックするということができていない
②記憶がすぐに消えてしまう場合は、認知能力の問題をカバーする工夫が必要となる
③記憶の保持に問題がある場合、紙にメモして机に貼り自然と目につくようにする
第2章:なぜあの人はいつも愚痴ばかりなのか?
・愚痴の多い人はほんとうにひどい目に遭っているのか
<ポイント>
①愚痴っぽい人は、けっして嫌な目にばかり遭っているわけではなく、ポジティブな出来事もたくさん経験している
②わざわざネガティブな出来事ばかりを選んで思い出しては嘆いている
③愚痴っぽい人は常にネガティブな気分で過ごしており、自分の気分に馴染むネガティブな出来事ばかりを記憶してしまう
第3章:なぜあの人は言うことがコロコロ変わるのか
・人間の記憶は意外とあっさりと書き換えられる
<ポイント>
・言うことがコロコロ変わる人物ばかりでなく、自分自身の記憶もいつの間にか自覚なしに変容している可能性がある
・自分自身で経験したことだと思い込んでいる記憶の中にも、じつは両親をはじめとする身近な人たちの経験を取り込んだもので自分自身では経験していないことがらがけっこう含まれている
・無用なトラブルを防ぐためにも、くれぐれも自分の記憶を絶対視しないよう注意したい
第4章:なぜ同じ経験をしているのに記憶がスレ違うのか
・「言ったつもり」のトラブルはなぜなくならないのか
<ポイント>
①記憶のスレ違いというのがけっして珍しいことではなく、だれもが日常的に悩まされており、気になっている
②「何度も経験している出来事は混同されやすい」という心理的メカニズムが絡んでいる
③普段から似たようなやりとりが多い場合は、別のときの記憶が紛れ込みやすいため、記憶のすれ違いが頻繁に起こりがち
第5章:なぜ昔の歌は覚えているのに最近の歌は覚えられないのか
・なぜ10代20代の思い出は特に鮮明なのか
<ポイント>
①40代も70代も、10代~20代のことはよく覚えている
②①の理由はいくつかの説があるが、私は自己のアイデンティティに関連付けて解釈する立場を取っている
③10代~20代の時期の記憶には、いまの自分の成り立ちをうまく説明するエピソードがたくさん詰まっており、そのためによく思い出す
第6章:なぜあの人と話すと記憶が変わっていくのか
・モチベーションの低い人物への対処法
<ポイント>
①私たちの過去は変えられる
②過去の出来事の意味を変えることは、十分に可能である
③過去の記憶を掘り起こし、何をやってもダメな自分、いくら頑張ってもダメな自分という自伝的記憶の意味づけを変えることで、過去の景色は変わり、モチベーションも上がってくることが期待される
まとめ
なぜ人は問題行動や、
認知のズレを繰り返すのか?
心理学的な知見をもとに、
原因と対策が本書で解説されています。
ざっとまとめたのがコチラ(↓)
<第1章>
・原因:同じミスを繰り返すのは、自分の行動を振り返らず、再発防止の工夫をしていない
・対策:メモを紙に書き、自然と目に入る場所に貼る
<第2章>
・原因:愚痴が多い人はネガティブな気分でいるため、ネガティブな記憶ばかりを思い出す
・対策:意識的に笑顔を作ることで気分を前向きにし、ポジティブな記憶を引き出す
<第3章>
・原因:記憶は簡単に書き換わる
・対策:自分自身の記憶も過信せず、他人との間で記憶が食い違っても冷静に対処する
<第4章>
・原因:似たようなやり取りの繰り返しで記憶が混同し、夫婦や職場での記憶のズレが起こりやすい
・対策:言い争いを避け、柔らかく話題を切り替える
<第5章>
・原因:10代~20代は自己のアイデンティティ形成に強く関わっているため、この時期の記憶は頻繁に想起されやすい
・対策:数年前の記憶が想起されにくくても問題なし
<第6章>
・原因:過去の辛い体験がモチベーションを低下の1つの要因である
・対策:ポジティブに再解釈することで、過去の辛い体験の意味を変え、モチベーションの向上につなげる
これらを知っていると、
対人関係に悩まされずにすみます。
自分はコントロールできても、
他人はコントロールできない。
問題行動や認知のズレに直面すると、
自分がストレスを抱えてしまう。
でも原因を見てみると、
他人の問題行動や認知のズレ、
実は自分にも起こる話であると気づく。

そう考えると、
相手を思いやる気持ちが生まれ、
対人関係のストレスもなくなる。
記憶/気分/解釈のメカニズムを知れば、
人間関係の悩みは無くなるのです。
仕事や家庭の悩みって、
人間関係に絡むことが多いですよね。
本書を読んで人間関係の対処法を学び、
ストレスフリーな人生を送りましょう。
本書のお値段は990円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。
お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学5年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)